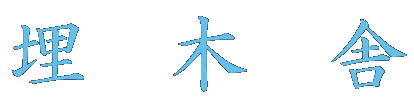勘六はイヤイヤと手をばたつかせる。無心な子供には於大の豊な微笑に害心のないのがわかるのだろうか、その於大がなにか口に含んだのを見ると、
「ウマ・・・・ウマ・・・・」
小さな舌をのぞかせて、またイヤイヤと母の膝で身もだえる。それでもお久はまだ勘六を手放さなかった。異様なものを口にした於大の顔を見つめ続けて呼吸をつめている。於大はふと泣きたくなった。甘いも、ふしぎな美味・・・・それすらうかつに口にできない猜疑と猜疑のはびこる世界。それも妙に悲しかったが、それ以上に於大の胸をうつものは、何ものも忘れ果てて子をかばおうとする母の心であった。
(子供というものは、このように愛おしいものであろうか・・・・?)
そう思うとあとから、お久に対して、かって感じたことのない羨望
が、ひたひたと心をひたして来るのであった。
華陽院は、於大に早く世継ぎをあげるようにと望んでいる。それはあるいは、こうした母の心を知らせたいからかもしれない。棉のいのちと女子の生き方を比較したのも、子供が母の代わりに生きる明日の世界へ喜びを繋ぐようにというさとし
だったのかも知れない。黒砂糖を味わい終えて、於大はまた勘六の方へ両手を出して、
「勘六どの来てみやれ」
「ウマ・・・ウマ・・・」
「これは祖母
さまのもとの船方のものがお土産に下された土佐のめずらしい飴じゃそうな。あまりに僅少ゆえ、殿にも差し上げられない珍奇なもの。舌がとろけるように甘いもの。さ、そなたに含ませて進ぜましょう」
言ったあとで、これもどうなることかと固くすくんでいる万を見やって、
「それ、お部屋さまにも差し上げてご覧なされ」
少し懐紙
に乗せた。万はおそるおそる受け取ってお久の方に前に差し出す。
ホーッと大きくお久の方の肩がゆれ、そのはずみにバタバタと膝の勘六が這いだした。まだ歩くよりも這うのが早い勘六だった。
「あ、これ・・・・」
もう一度手を振ったときには、もう勘六は於大の膝に着いて、
「ウマ・・・・ウマ・・・・」
と、口を開いた。於大はその勘六に、身をかがめて頬ずりした。そして、また自分でも小さなかけらを口にしながら、
「さ、ご賞味なされ、三河の国にはないものぞ」
そっと柔らかい勘六の唇に指を触れたとき、はじめてハッと、この使いを自分に命じた華陽院の心の解けてゆくのがわかった。
幼児の唇はまたなんとなめらかな感触で女の心をとろかす力を持っているものか・・・・於大の方は肚の底から自分も子供が欲しくなった。そうさせようとして勘六のもとへ使いさせた母の心が、強い愛着で心にとおった勘六は、はじめて舌に残った砂糖の甘さを、小さな肩をきゅっと寄せて賞味しているし、その母もまた、わが子に遅れじとあわててそれを含んでいった。この方はまだ大きく瞳孔
を開いたままで、不安な味覚にこらしきっている。牡丹の花の向こうから、しずかに夕風が立ちそめた。 |