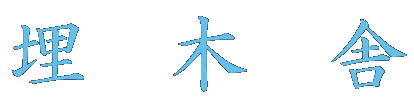一文字に扉を開いた大手城門の積雪は、かがり火に映えてあやしいまでに白かった。
そしてその空間を十秒間隔ほどに槍をかかえた足軽が右に往き、左に歩いた。寒さを防ぐために歩くのではない。ここを守れと命ぜられた天野康景が、十六人の足軽どもを数百人に見せようとして姿勢を変えては、右往左往させているのである。
あちこちで焚きつづけるかがり火が、くっきりと城の全景を夜空に浮かべている。そこへ馳せ戻った酒井中次の手の者がやぐらに駆け上がって大太鼓を打ちだしたので、城全体が活気をはらんだ生き物のように見え出した。甲斐の小人、山県三郎兵衛昌景は一気に城へ雪崩
れ込もうとして、大手前二丁の位置で 「待てッ!」 とはやりたつ手勢をおさえて馬を停めた。いよいよ太鼓は鳴りつづき、かがり火は明るさを増してゆく。
一文字に開いた城門から傷ついた浜松勢が三々五々と入ってゆくが、そうしたことには関わりなく堅めの兵は整然と守備についている。
「おかしい?
下知があるまで動くな」
昌景は小首をかしげたまま馬首をめぐらして右後方の勝頼の陣へ駆けつけた。
勝頼はこれも馬を停め、吹雪く雪に小手をかざして城を見上げている。
「四郎さま」
「三郎兵衛か。城の様子はどうだ」
「もはや残る者はないと存じましたに」
「あの太鼓は何を触れているのであろう?」
「四郎さまにもご合点がゆきませぬか」
「おかしなことをするものじゃ」
そこへまた雪を蹴って小山田信茂が駆けつけた。信茂は眉毛に白く雪をつけたまま、
「まだ守備の者が残っていたとみえますなあ」
勝頼はうなずいて、
「誰ぞ梅雪がもとへやって見よ。人馬ともに疲れている。無理な戦はもう出来ぬぞ」
「はい」
と答えて、馬廻りの一人が最右翼に押して来ている穴山梅雪の陣へかけだした。
と、そのころ、総懸かり門からふたたび雪の中へまぎれ出た大久保忠世は二十六人の鉄砲足軽を引き連れて、穴山勢のわきから犀ヶ崖の崖下へすすんでいた。
手足が凍りそうで、そのうえひどく下腹がしぶってゆく。ぐっと力を入れると水のような排泄物がちびりと股間へ洩れていった。
忠世は生真面目な表情で、
「お館さま、ごめんなされませ」
と言ってまた歩いた。馬の上で洩らした糞を、焼き味噌にした家康の勝ち気さが想い出されたのだ。
崖ぎわには膝を歿するほどに雪がたまっていた。そこで忠世は行進を止めると、二十六挺の鉄砲を穴山勢の背後に向けさせた。
「ならいなどはどうでもよい。点火してぶっ放したら、一世一代の声でわめけ」
火縄に火が点いた。火薬の匂いが濃くただよって、やがてダダーンと二十六挺
── というよりも浜松城の全火力がものすさまじい響波をあたりにまきちらした。
つづいてワーッという、寒さしのぎの喊声
である。と、不意をうたれた穴山勢は蟻
の巣をあばいたように動きだした。
「もう一発・・・・」
胴震いをおさえて言うと、またちびりと忠世の尻から排泄物がもれた。 |