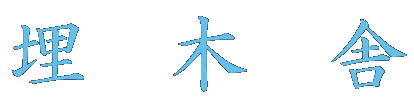家康はもはや何も考えなかった。
考えていることは、いかなることがあっても武田勢に屈せぬ男の存在を示すこと、ただそれ一つであった。
いや、ただ武田勢だけではない。いかなる大軍、いかなる戦略をもってしても、腑に落ちぬ相手に膝などは断じて屈せぬ。それが家康なのだと、運命に向かい、天地に向って叫びかける一戦だった。
運なくば皆殺しにするがよい。
その時には生かしておいても益なき奴と、神がわざわざ裁いたもの・・・・そう信じて死ぬつもりの心境だった。
いつもと違う面もむけられぬ家康のはげしさに触れて、各隊は三方ヶ原めざして行動を起こした。
が
──
一方の武田勢はそうした家康の決意の前に、何を考え、どう動いていたであろうか?
武田勢の二十二日早朝の実数は二万七千余であった。信玄はこれをひきいて粛々と天竜川を渡って三方ヶ原にかかった。
どこまでも用心深く、飯尾
ヶ原 にかかると行進を止めてすぐに物見の報告を待った。
信玄はいまだに家康が玉砕を期して挑みかかって来るとは信じていない。
「もし、この大軍に決戦を挑んで来るようなら、家康は思うたよりはるかに劣るたわけと言わねばならぬ」
だが勝頼の意見はその反対だった。
「いいや、家康は必ず、ここで食い止めようといたしまする。この勝頼にしても、一戦もせずに通すなど・・・・そのようなことはいやしますまい」
まだあたりの見透せぬ冬の朝霧の中で信玄は腹をゆすって笑った。
「すると家康は勝頼とトントンの無思慮者か。ハッハッハ」
そこへ偵察にやってあった上原
能登守 が馳せ戻った。上原能登は小
田山 信茂
の配下で、前夜から犀ヶ崖へ深く入って、浜松勢の動きを逐一
見届けて来たのである。
小山田と馬場信春は、能登守を引き連れて信玄の前へやって来た。
「能登、そちの見たまま思うままをおん大将に申し上げよ」
「はッ」
と答えた能登は自分でも首をかしげながら、
「浜松勢は九隊の総勢を横一重の鶴翼陣に構えてござりまする」
「なにッ、それはまことか」
信玄はびっくりしたように身を乗り出し、床几が大きくきしんでいった。
「はい。それにひどく旗色がととのわず、浮き足立っているかに見えましたが」
「お父上!」
と、勝頼の端麗な頬に鋭い笑いがうかんでいった。
「勝頼の眼もそう狂ってはおりませぬ」
「うーむ」
信玄はうなった。わが前にあの備えのない鶴翼陣で立ちふさがった。そう聞けば相手の心は手に取るようにわかる信玄だった。
「そうか、死にに来たのか」
その決心の猛々しさに微笑を誘われたが、何と言っても思慮は足らぬと言わなければなるまい。
大将がその決心でも戦は一人でするのではない。この大軍を前にしてそのような構えでは旗色の揃おうはずはなかった。
「そうか。やっぱりのう、まだ若い」
|