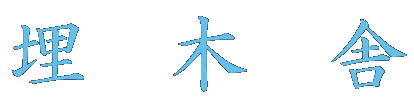到着を知らせる法螺が戦列から聞こえてきた。
元亀
元年 (1570) の七月八日。
信長と旗を並べて戦って、
「── 三河勢こそ日本一!」
めったに人を褒めぬ信長にそう言わしめて戻って来たのだ。男対男の面目は立った。
家康は、自分を漢
の高祖 にたとえ、本多平八郎を張飛
にたとえた信長の言葉を思い出しながら、自分の居城の城門をくぐった。
両側に、ずらりと出迎えた留守の者に、いつもと変わらぬ穏やかな表情を見せられる ──
それが帰る者にとってはこの上ないよろこび。
家康はみんなに眼顔で会釈
を返しながら第二の矢倉門にかかろうとして、出迎え人の中にまじった一つの顔にハッと大きく胸を打たれた。
その顔はかっての曳馬野
城主、飯尾豊前の妻の顔、いや西郷弥佐衛門正勝が孫娘お愛の顔だったと思い直した。
それにしても、今日のお愛の顔はなんと心に残る顔であろうか。
際立
った色の白さのせいもあろう、まばゆいほどに光った珠が、さりげなく路傍の草に混じっている感じだった。
いや、その珠はあやしい憂いの露をふくんでいる。泣きたいような、すがるような、無視するような挑むような・・・・
あるいは心の中の悲しみにさからって、主君の凱旋を喜ぼうとつとめている、その意志と自然の交錯した美かも知れない。
家康は思わず馬を停めそうになってあわてて鐙
を馬腹にあてた。
それなのに、
「お愛か・・・・」 と、口ではすでに呼んでいた。
「はい、つつがないご凱旋、謹んでおよろこび申し上げまする」
家康は狼狽した。
「そなたは・・・・いや、そちは、そうだ、城に出て来ていたのだったな」
われにもなく言葉が乱れ、頬がポーッと熱くなった。
むろん、それ以上に言葉をかける場合ではなかった。わざと視線を正面へ据え直し、ゆったりと馬を歩かせながら、それから後に会釈した人の顔に覚えはなかった。
家康はおかしくなった。
信長にさえ一歩もゆずらなかったほどの者が、一人の後家を見た刹那
、静心を失うとは何であろうか?。
しばらく女子を近づけなかったせいとも思えたし、自分にはそうした欲望が人一倍逞しいのかと思われた。
すると、おかしなことに、それらを否定して
「縁 ──」 という字がふと頭に浮かんで来た
この世には人智で計れぬ、ある 「力」 がうごいている。その力が自分にお愛を注目せよと命じているのではなかろうか?
家康は大玄関前で馬をおりると、そこにはりめぐらされた幔幕の中へ入っていった。
(男というものは、女が欲しゅうなるとさまざまな理窟をつけるものだ・・・・)
設けの床几に腰をおろして、自分の妄想を笑おうと思ったとき、
「麦湯でござりまする」
またお愛が彼の前に現れた。 |