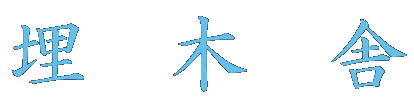すでに女として。お部屋さまとして、さらに勘六君
の生母として十八歳になっているお久には、於大のお屋敷さまは子供に見えた。その子供がいつもぐいぐいお久を圧迫する。その圧迫がただに正室という名目から来るのだったら、お久はこうもいら立たずに済んだであろう。が、それはお久が想像していた少女とは全然違った人柄からくるものだった。たとえばつきたての柔らかい餅
に、しっとりと圧 えこまれているような重量感。綿の種を植えよと言われた時も、耕作の経験はありませぬ、と答えると、
「お殿さま・・・・というよりも、勘六どののお役にいつか立ちましょう。於大も知らぬことをやってみます。そなたもなあ」
ふわりと圧えて二の句をつがせなかった。
(こんなはずではなかった・・・・?)
お久はよくそれを思う。嫁いで来たら毒害しようといきまく広忠をなだめたのはお久であった。
同族松平左近乗正の娘として、いわば落日の中に立たせられた幼主を、織田信秀に内通している大叔父、松平信定一派の陰謀の手から守るため、わざわざ選び出されて側女
にあげられたお久であった。そのお久がいつか十四の於大におさえこまれたばかりでなく、広忠までが、毒害のことなど忘れ果てて於大に寵
を移してゆく。
(── 華陽院さまはなみなみならぬご利発のお方ゆえ、お屋敷さまへ何かと知恵をつけさせられる)
このままではいつか自分や勘六はこの城から浮き出たものになりそうで、じりじりしているお久であった。
そのお久の眼の前で、あやしく黒い煉
り薬に似たものを勘六どのに食べさせようとする。
お久がわざわざ勘六をわが手で育てているのは、これも信定一派への警戒からだったが、いまはその警戒の相手は二つに殖えている。
「勘六どの、これへ・・・・」
於大に方にさし招かれ、無心に立って勘六がヨチヨチと幼い笑顔で近づき出すと、
「あれっ、勘六さまは・・・・」
お久はそれをサッと横から抱き取った。目尻がきりりと吊
って、それがピクピクと震えている。血の気のない唇は庭の青葉の返し照りで、紙のように白く見えた。
とっさのこととて、その場をつくろう言葉も出ぬらしく、
「お屋敷さまの・・・・お屋敷さまの、お膝に、もしも尿
をかけたら何とします。ご・・・・ご・・・・ご無礼でございましょう」
於大はその狼狽を予期していた。華陽院にしても、むろんお久のせりはわかっていよう。それなのに、こうした使いを・・・・
於大に方は苦しかった。といっても、この母子から目をそらしたら、いっそう気まずい空気をかもしてゆくに違いない。ニコニコと笑ったままで、於大は膝に広げた黒砂糖をそっと欠いて自分に口にふくんでいった。甘かった。ツーンと歯にしみて、それから口いっぱいに広がってゆく。
お久はブルブル震えながら、まだしっかりと勘六を抱いていた。それは子のために見せる母の大慈の崇厳な一面と、いまの於大には映る。
「さ、勘六どの」
と、また於大は言った。 |