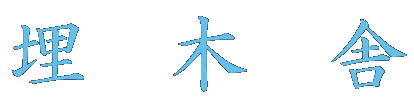「たしかに!」
と、忠次が、これも解けきれぬ表情で首をかしげた。
「殿がここにあると知っていながら、連絡もせずに引き揚げる・・・腑に落ちぬことながら、すでに先手は大平並木に達しまする」
「大平並木といえば城から一里、おかしなことがあるものじゃな」
「全くもっておかしなこと。後詰めもうしろを警戒しながら城を出て、城中ひっそりと静まり返ってござりまする」
「ふーむ」
わざと仰々
しく首をかしげながら、元康はまたおかしさがこみあげた。
いや、それはおかしさというよりも、泣くか笑うかせずにはいられぬ至妙は感動といってよかった。
十有余年続いて来た灰色の人生の中で希望の光はほとんどなかった。その代わりに絶望ならばいくらもあった。
その絶望にならされて、幸福などは自分にないもののように考えられていたのに、やはりそうでもないらしい。じっと心を静め、気を練って耐えてくると、天も悲運に飽きて来て、やがて幸福をもたらすものらしい。
大樹寺へ引き揚げる時が元康の悲運の絶頂であった。
ようやくそれに耐え得たのは、考えてみれば登誉上人や寺の大衆の力づけであった。
その寺の助勢は祖先の徳行が基をなしている。
(そうか、祖先はやはり死んではおられなかったのか)
その感動をぐっとのんで、
「田中次郎右衛門め、そうか。城を捨ておったか。やむを得ぬ。捨てた城ならば駿府の指図はなくとも拾わずには相なるまい」
いいながらずっと一座を見回すと、元康の心を知らぬ天野
康景 は、
「追い討ちをかけましょうか」
と、血気にいった。
「たわけめ」 と、元康は軽く叱った。
「われらはどこまでも今川家への義を踏むものだ。捨てた城ゆえ、拾うというのがわからんのか」
「なるほど、それはよい思案!」
登誉上人がはじめてそれに気づいたように、ポンと中啓で自分の膝をたたいたとき、
「では・・・・」
と、元康は立ち上がった。
「空城
一つ拾いに参る。すぐ勢揃いするように」
そしてはじめて頬をくずすと、声をあげて笑ってしまった。
「空城を一つ拾いに行く?」
「ほんとに城を捨てて逃げたのか」
「待てば海路の日和
、とはこのこと、急げや用意を」
それは苦節十年の岡崎の衆にとっても夢みるような出来事だった。
総大将の義元が討たれたことで、岡崎衆があれほど待ち望んだ帰城の日がやって来ようとは。
元康を真っ先にして、まだ落ちきらぬ斜陽の中をみんなは不思議な感慨
で進んだ。城の大手へかかると、そっと自分のほほをつねってみる者すらあった。
元康は大手多門の前で馬をおりて手綱を本多平八郎に渡した。
タケ行き八間四尺、ハリ行き二間四尺のこの門はそのままくぐるにしのびない門であった。生母於大の方の輿を向えた門。自分を人質に送り出した門。
その門をじっと下からにらみあげると、八幡
曲輪 の老松にあたる風の音が遠い遠い魂の声となって、あたりの大地を揺り起こしている感じであった。
|