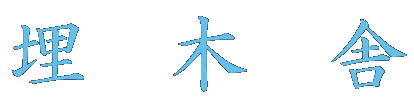二度目の喝棒は次郎三郎をひるました。老師のどこにこれほど激しい気魄が残っていたのか、その驚きもあったが、こうした無理が消えかけている生命の灯に触ってはと、その怖れもあって思わず平伏してしまった。
雪斎は横になった。荒い呼吸がしばらく室内にこもってゆくと、次郎三郎はまた声を盗んで泣き出した。
「元信・・・・」
「は・・・・はい」
お許はどうしてそう、知らぬことを簡単に口にするのだ・・・・お許はまだ、妻も子も持っていまい。持たぬものの味はわからぬ。味も知らぬ者が忘れますとは何たる思い上がった根性か」
「はい・・・・」
「妻子というが、そのように容易に忘れ得られるものならば、世間にその愛情での苦悩は一切ないはずじゃ」
次郎三郎は自分の軽率な答えが老いた老師を怒らせたのならば詫びたかった。この師の教えとあらば忍びがたきを忍ぶつもりで答えたのだ。
「お許の母はいまだにお許の無事を祈って、阿古居の城から何かと心を通わせてくる・・・・これが母の心・・・・よいか・・・・母の心はまた、もっとも自然な天地の心の現われじゃ」
「はい」
「それをやすやすと人為で断つというのは天地の心への反逆、また・・・・」
と、言いかけて、手を振って水を求めて、
「お許が御所の命に服さぬと申したら、御所がそのまま、お許をゆるすと思うか。これは小児の妄想
だと心づかぬか」
次郎三郎はサッと頭の血が下がった。
(そうであった!)
一人の松平次郎三郎などが、ひた押しに京を目指す義元の前で、軍律にあらがえるものではなかった。彼は老いたる師をなぐさめようとして、ことごとく、失望させる無思慮ぶりをさらけ出してしまったのだ。
「お許しくださりませ!」
そういうと、こんどは突風に似た号泣
が彼の体を占領した。
雪斎はふたたび眼を閉じた。
いつか窓の陽はうごいて、光も淡くなっている。小鳥も鳴いてはいなかった。
次郎三郎の号泣が止むと、
「お帰りなされ」
と、雪斎は言った。
「この答えはのう、やはり黄泉
で聞くとしよう。よいか。誤った工夫では、わしの魂は救われぬ。お許の身もほろぶ。そして地上の修羅はいつまでも続いてゆく」
「工夫しまする。必ず! お許し・・・・」
「よい、山門に誰か来たようじゃ。ことによると御所も見えられるかも知れぬ。お帰りなされ」
「では・・・・これでお別れでござりまするか」
「それ、またそのようなことを、今の言葉忘れたか。別れでのうて、来る春からお許の体にわしの芽をかくすのじゃ」
「はい」
「途中で誰かに会たら、わしに呼ばれたと言うではないぞ。お許の方から、いつものとおり、経義
をたずねに参ったら、わしが病気で、果たせなかったと言うのじゃぞ」
「はい。では元信、これにてお暇
いたしまする」
「体をいとえよ」
「はい」
「短気を起こすな。短気は人を盲にするぞ」
「は・・・・はい」 |