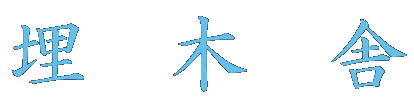次郎三郎は、自分自身の坐らされている位置をはじめてはっきりえお見せつけられた気がした。
今川義元の姪と結ばれ、今川家縁類の端につながることで松平家の安泰
を計り得ると考えたのは、誤算ではなかったにしても、決して利益とのみは言い切れなかった。
雪斎の言う通り、それはむしろ今川義元が、松平次郎三郎をわが薬籠中
にとりこめる巧妙な政略にもなっていたのだ。
「よいかの、お許の内室と子供とは人質になっている。そしてお許は斬り死にを命じられた・・・・」
またつぶやくように念を押されて、次郎三郎はウームと下腹部へ力を入れた。
「ここでご返事申し上げねばなりませぬか」
雪斎はそっと眼を開いて、かすかに首を振って微笑した。
「わしが、お許に残す、最後の大事な公案じゃ。だが・・・・応えの浮かんだ時には、わしはもはや死んでいよう。そこでのう元信・・・・」
「はい」
「お許は、その工夫
を、そのとき、実地の駆け引きでわしの霊に見せねばならぬ」
「はい」
「わしがなぜ、このような公案をお許に残すか? わしがなぜ御所にお許を動かす策を献ぜず、逆にお許をさきに枕辺に呼び寄せたか・・・・」
次郎三郎は不意に肩をふるわして泣き出した。雪斎長老が義元よりも深く自分を愛してくれているのが、これほどハッキリと身にしみたことはなかった。
いや、それは世の常の小さな愛情ではないはずだった。仏道の究極を行わんとして、不殺の剣に武装し、三軍を叱咤
して来た豪僧の悲願の血脈を伝えようとする、きびしく高い愛情と受け取るべきであった。
次郎三郎が肩をふるわして泣く間、雪斎はまた眼を閉じて、あるかなきかの気息をためているようだった。
「長老さま!
いまお答えいたしとうござりまする」
涙を振り払って次郎三郎は叫ぶように言い放った。
死後では心もとない。いまハッキリと答えて、老師の安らかな微笑が見たいと、若い情熱がつい知らず言葉になった。
「ほほう。いまただちにこの公案が解けるというのか」
「はい。解けまする」
「聞こう。申してみよ」
「元信は、駿府へ残した妻子のことなど忘れまする」
「忘れて斬り死にするというのか」
「それは分りませぬ」
「なぜわからぬ!」
斬り込むはげしさで問い返されて、次郎三郎の頬は紅のように熱していった。
「妻子を忘れて大局を睨みまする。元信が郎党とともに斬り死にして、それが不殺のまことにかないまするならば、潔
く斬り死にする。が、その反対と見てとったら、たとえ御所の命なりと、断固
これを退けまする!」
「たわけめッ!」
ハッと身を引こうとしたときに、次郎三郎の左の肩は微塵になれとその場にあった喝棒
を食っていた。
「思い上がった高慢者めッ、いま一度申してみよ」
「はい、何度でも申しまする。たとえ御所の命なりと・・・・」
いいかけると今度は頭上へぴしりとはげしい一撃だった。
|