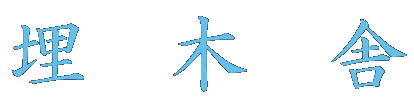新八郎忠俊はもともと大久保氏ではなかった。彼の少年時代まで代々、宇津を称していたのが新八郎忠俊の代になって、大窪と名乗り、それからさらに大久保ろ改めた。
彼の少年時に、越前の武芸者大窪
藤五郎 が、岡崎にあって、新八郎の武勇をほめ、
「──
わが姓を後世に伝える者あるとすれば、それは新八郎忠俊のみ」
そういったのがひどく彼を感動させたと見え、
「── さらば大窪に」 とあっさり改姓したという淡々水のごとき半面に、いったんこうと思い決めると、脇目もふらぬ情の強さを持っていた。
新八郎は倅と甥をしたがえて、信広の取り込められている対屋
にやって来た。
「本日只今より、大久保新八郎忠俊、命
によって織田三郎五郎が見張りをつかまつる」
あたりにとどろきわたる声を聞いて、番卒は丁寧に一礼して去ってゆく。
新八郎は鹿垣の中に入った。そしてひっそりと閉ざされている厠
の小窓に近づき、
「織田の小せがれ、明早朝に旅立ちじゃ、用意さっしゃれ」
と、声をかけた。中から足音が窓に近づいた。さらりと障子を開けたのは、雪斎の計らいで特に信広につけられた二人の侍女のうちの一人であった。新八郎はその女の肩越しに、中の信広を覗き込んだ。
信広は部屋の中央に、きちんと四角に坐っていた。頬も唇も紙のように白く、その眼は憔悴に光っていたが、しかしそれも不敵な光ではなかった。
「お身が大久保忠俊か」
言ったとたんに瞼がぴくぴくと痙攣
した。顔も目鼻立ちも信長によく似ている。が、それらはいかにも品よくみなほとまわり小さかった。
おそらく胸の奥に息づく肝はもっともっと小さいのに違いない。
「なんじゃと、聞こえなかったわ。もう少し男らしく大きな声で言ってみよ」
新八郎は意地悪く耳に小手をかざして言った。
「お身が大久保忠俊か」
「そうじゃ」
「旅と申すと、人質交換のこと相整ったと見えるな」
「おれは知らぬ。そのようなことは」
「行く先は知っているであろう。どこまでじゃ」
「とんと知らぬな、行ってみたらわかるだろう」
信広はわなわなと拳をふるわしてうなだれた。
「特に用意もあるまいが、よいかな、明朝の出発だぞ」
そう言いおいて新八郎は窓を離れた。
倅の忠勝と甥の忠世とは、この傍若無人な新八郎の振る舞いに、あきれて顔を見合っている。
「忠世、おぬしは井伊次郎どのがもとへ参って馬四頭を借りて参れ、われら四人、西野まで行く馬じゃ。名馬はいらぬぞ」
「父上」
と、忠勝がそばから口を出した。
「信広どのだけ輿
にされては」
「何ッ!」 と、新八郎は噛みつくような眼をして、
「おぬしと忠世とでかついでゆくなら輿にせよ」
忠世はニヤリと笑って、そのまま馬を借りに走った。 |