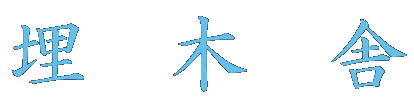雅楽助はさり気ない表情ですばらく新八郎を見返していた。広間の駆け引きでは押され気味の雅楽助も、家中の士の動かし方には自信があった。
雪斎や平手政秀を大人とすると、これは頑童
ほどの単純さしかもっていない。
「新八どの」
「なんじゃ」
「おぬしはいったい幾つになられた」
「これはまた妙なことを。わしはまだ二十代の若者に、少しも劣らぬ気概で戦うて来ているわ」
「おぬし、四十より五十に近かろう。五十には五十の思慮があるものぞ」
「ハッハッハ、それでわしに信広護送を押し付けようとしても、それはまっぴらじゃ」
「まっぴらならば頼むまい。だがおぬしの考え方は、行きを思うてもどりがない。なるほど行く時は信広どのの護送じゃが、もどりは竹千代さまがお供のはず。わしはな、先君を岡崎の城に迎えたおぬしに、こんどもまた竹千代さまを迎えさせるが、おぬしら一族の武勇に応える道と心得、頼んだのだ」
「なに・・・・」
と新八郎は声をおとした。
雅楽助は手を振って音の言葉をさえぎりながら、
「いずれも方、いかが思われる? この雅楽助の計らいを」
むろん一同に反対のあろうはずはなかった。
「なに・・・・」
と、また新八郎は首をおとして雅楽助に近づいた。
新八郎が気にしているのはやはり自分の無学さであり、世なれなさであった。もし相手に気押されて、人質の竹千代に肩身の狭い思いをさせてはと、それが心にかかっていりのである。
「するとおぬしたち全部が全部、わしに送って行けというのだな」
雅楽助はうなずいた。
「では、万一この新八がこらえ性もなく織田方の家臣をしかりとばしても、文句はないか」
「任せた以上、誰が口を出すものか」
新八はそこではじめて吐息をしながら一族をかえりみた。
「ではわれらで引き受けよう。場所が西野とあれば供の人数はいっさい不用じゃ」
「なに、供は要らぬと」
「さよう。わしのほかにあと二人、倅
五郎 右衛
門 忠勝
(後の新八郎) と、甥の七朗右衛門忠世の両名を引き連れる。甚四郎も異存はなかろう」
甚四郎は忠世の父であり、新八郎の弟だった。
「異存はない。が、ただ三人だけでは竹千代さまお迎えするに軽きにすぎることはないか」
「ばかものめ!」
と、新八郎は弟をしかった。
「三河はわれらが領内、領内は城の内も同然じゃ。城うちならば一人歩きも威はおとさぬ。では五郎
右衛 、七郎
右衛 、参ろうぞ」
雅楽助は思わず心で北叟
笑 んだ。彼の想像していた通り新八郎忠俊は、無策の策、武装のままで行く気らしい。
「このままで参るのか」
と倅の五郎右衛門が訊 き返すと、新八郎はこれもはげしくしかりとばした。
「たわけ者め、われらはな、盗まれ者を取り返しに、盗人
の子を送って行くのだ。長着物で行けると思うか。この心を忘れて気後れすると、おぬしも甥もこの新八が叩
っ斬る」
そう言い放って、そのまま城内へ入ってゆく。鹿垣
に取り込められた織田信広を、決まると同時に護衛しなければ ── そうした気性の新八郎だった。 |