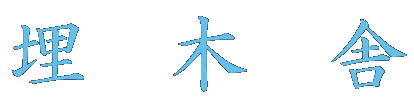「盃を花嫁からとは、誰が決めた」
信長がわめくと、平手政秀は微笑を含んで、
「婚礼のしきたりでございますれば」
厄介
な駄々っ子と、いいたげな眼差しをとりなすように濃姫に移した。濃姫は出しかけた手を引いて、ふたたび眸
をけわしくする。
変わり者 ── という以上に、いまは屈辱に身内の震える濃姫だった。だが、信長はそうした相手の感情などは微塵
も忖度 する様子はなく、
「なにッ、しきたりじゃと・・・・しきたりならば従わぬぞ」
声高にわめきちらして、
「これはそもそもなみの婚礼ではない。のう、姫」
と、花嫁に向き直った。
「尾張の大うつけ者と、美濃のうつけ者が婚礼じゃ。花嫁の父御
はどうして花婿の寝首をかかせようかと肝胆
をくだき、花婿の父親はどうして舅の鉾先
を封じようかと策をめぐらす。そのような婚礼に何のしきたりぞ。盃はまずこの信長から乾して取らそう」
「これ・・・・」
たまりかねてまた土田御前が膝をたたいが、信長の耳には入らなかった。
むろんこの席に父の信秀はいなかった。彼は古渡
の城で、いま今川勢の進攻をどう食い止めようかと必死で策を練っている。この婚礼もいわばその一連の作戦の一つであった。
「盃も逆がよい。最初に大きなものじゃ。さ、なみなみと注げ!なみなみと」
信長は盃を取って二人の少女に突きつけた。
一切の習慣に反逆して、常識の埒
外に立とうとする信長の反骨は、もはや蔽
うべくもない性格になりつつあった。
平手政秀はそれを知っている。いや他の三家老もまたこの性格を、ある時は苦々しく、ある時は好もしく見て来ている。
それにしても婚礼の席へ埃
まみれの平服で現れ、固めの盃を自分から先に取るのはあまり粗暴に過ぎると思えた。
何よりも濃姫の心の打撃が思いやられる。こうしたことが舅の道三の許へ聞こえることもはばかられた。
と、いって、吉法師の昔から一度言い出したら聞き入れる信長ではなかった。
「姫、許されよ」
政秀は小声で言って、ひざの白扇を笑いながら閉ざしたり開いたりしている。
信長はついに、一升一合の大盃になみなみと酒を注がせた。
「よしよし、これでよい。これを一気に乾してな、その上で肴
を添えて嫁にさそう。見事受けきられたら、まずまず似合いのうつけ者じゃ」
じろりと一座を睨みまわしてそれから首をさしのべた。
身丈
も高かったが首も長い。のどぼとけのあたりを音を立てて吸われて通る酒を見ているうちに、濃姫はふと心が和
らいだ。
悪意あっての悪罵
でなく、これはまだそのまま腕白
ざかりの童 なのではなかろうか。
信長はとうとう、息もつかずに大盃をのみ乾した。そしてその盃を少女に返すと、
「さ、姫に注げ。よいか姫、肴をとらすぞ」
舌なめずりしながら、すっくと姫の前に立った。 |