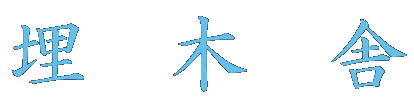姫はこれも負けてはいなかった。斉藤道三が娘という誇りもあったが、それ以上に、これも性来の勝気の虫がすむらしい。
相手の風貌の中に、腕白な童のなごりを読み取ると、良人としての頼りなさを感じる前に、
(こんな子供ひとり・・・・)
と、強い反撥がわくのである。
姫は臆した色もなく、これも大盃を取り上げた。しかしなみなみとは注がせずに、二、三滴銚子の口から滴り落ちると、つと盃を引いてしまった。
信長はニヤリとして白扇お開いた。
「よいか、肴
をつかまつるぞ」
ゆらりと右手を水平に、左手をひざに当てると、朗々と幸若
をうたいながら舞いだした。
「・・・・思えばこの世はついのすみ家に非
ず、草葉におく白露、水にやどる月より猶
あやし。金谷に花を詠じし栄華は、先立ちて無常の風にさそわるる・・・・」
「これ!」
と、また土田御前がひざをたたいた。
婚礼の席にはなんと不吉な
「敦盛 ──」 を。一座の人々も思わず顔を見合わせたが、信長はいよいよ声を張った。
「・・・・人間五十年、下天
のうちをくらぶれば、夢まぼろしのごとくなり。ひとたび生をうけ、滅せぬもののあるべきや・・・・」
古びた城。よく徹
る声。それは不思議な厳しさでこの変転の常ない現世に生きる人々の胸をえぐり、魂
をおののかせた。
濃姫はいつかまた信長への競いの矛先
をそらされてゆきそうだった。
「 ── ただのうつけ者ではあるまい」
そういった父の言葉が今さらのように胸によみがえり、全身はひとりでに引き緊まった。
舞い終わると濃姫は盃をいただいた。唇を触れて数滴の酒がのどを通るとき、ふと人生の不思議さが思われた。
(これで自分は信長の妻と決まってゆくのだろうか・・・・)
生涯信長の守が出来るかと言われた言葉が、ことりと音を立てて咽喉
から胸へ通っていった。
「めでたい!」
と、突然信長は言った。
「めでたいが、このうえ、祝い酒を汲むことは相ならん。岡崎から安祥
へ・・・・すでに戦雲は動いている。用意して父の指図を待ちうけよ」
平手政秀と内藤勝助がニヤリと顔を見合って笑った。
信長は何事もなかったかのように立ち上がった。
「姫。参れ」
「はい」
それは凄まじい勢いで胸を貫く否めぬ言葉の矢であった。姫が立ち上がると、
「大丈夫かな」
と、林 新五郎
が政秀にささやいた。
「若は知ってござるであろうか?」
政秀は生真面目にこくりとして、
「自然のことじゃ。それに姫が年上じゃで」
そのときには信長はもう姫の手を取って、さっさと奥の居間への廊下を渡っているのであった。
「ふッふッふ」
と、誰かが笑い、それからシーッとそれをおさえた。 |