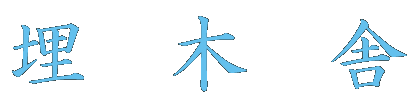埋木舎に移ってから三年後の天保五年 (1834) の夏、直弼は藩主直亮の招きで、諸侯の養子候補として江戸へ向かうことになった。直弼は埋木舎を出る時、再びここでの窮乏生活に戻ることもあるまいと喜び知人を集めて別れの宴すら行ったのでった。
桜田の藩邸で弟直恭とともに居て養子の面接を受けたが直弼は落第してしまった。弟直恭の方は日向延岡藩に縁組が決まり、名を内藤政義と改め、能登守に任じ七万石の城主となったのである。
直弼はさらに一年ばかり江戸藩邸にむなしく時を過ごした。その間も勉学は忘れず、兵学は西村台四郎義行に就いて、山鹿流の兵法を学んでいる。ある日、湯島の聖堂見物に出かけた折、神田橋で大名行列に出くわした。それが弟の延岡藩の行列とわかると、感無量のものがあったであろう。直弼は孤独に耐えてか、自分自身を励ます気持ちからか、藩邸へ卻から、鉄三郎自記するところの
「埋木舎記」 を就筆した。 |
うもれ木の屋と名づけたりし意を、問ふ人のありけるにつきて云ひけらく、いにしへに、源三位は埋木を以って、今はの歌に、花さくこともなかりしといひ、家隆二位は、此を以って祝ひ寄せ、氷の下に春を待つなど、甚心はさまざまなり。おのれは
「世の中をよそに見つつも埋木の埋もれてをらむ心なき身は」 といひき、これを四とせばかり過にしあとのことにして、この名、いまいひそめしにあらず。さるに、こたび、とみの事とて、ここにめしよせられて添御館をかさせ給ひしを、かく賤しき名をもてしるせること、いとはしたなく覚え、世の人々の心にも、そむくべきなれど、今しばしのすまひを、何とかはよぶべきとて、古郷の軒端に書きつけたりけるを、やがて物にしるしつつ名づけし故よしは、はじめの歌にて知るべし。これ世を厭ふにもあらず、はた世を貪るごとき、かよわき心しおかざれば、望み願ふこともあらず。ただうもれ木の籠り居て、なすべき業をなさましと、おもひて設けし名にこそといらへしままを埋木舎のこと葉とす。
天保五年の冬江戸にをりて 直 弼 |
|
翌天保六年八月、直弼は一切の名誉を捨て埋木舎にて文武の修練に打ちこもうと再び、彦根の埋木舎に帰って来たのである。直弼が江戸を発つ時、家臣の三浦十郎左衛門は
「御前には空敷御帰国遊ばされ候の御心中、其頃出府仕居り、御発駕を見掛奉り恐察奉り候」 という書簡を送ったのであるが、養子縁組も出来ず、一生埋木舎での世捨て人が決まったように思われた直弼を涙して見送った家臣の気持ちがよくわかるものだ。
なぜ養子縁組が決まらなかったかの憶測は、才が長けすぎていたとか、顔がこわくいかつすぎたとか、人相学上死相が出ていたとか言われるが確証はない。
埋木舎における日夜孜々としての修練の様子は次章以降で詳しく述べるが
「予は一日に二時 (四時間) 眠れば足る」 といって寝食を忘れて修練に精進したのである。
このような埋木舎での人格形成がなかったとしたならば、後は、藩主となり、大老として幕末急を告げた国家の安泰のため開国を断行し、欧米の植民地主義の侵略から我が国を守り得た大器量は生まれなかったのである。
かかる大政治家のスケールは凡人には理解されず、血気盛んな水戸や薩摩の野蛮な浪士どもに桜田においてテロを受け生命を落とすことは真に惜しんで余りあるのであるが埋木舎時代にこれらの運命を誰が予期出来たであろうか。 |
| 「埋木舎」 ─ 井伊直弼の青春時代 ─ 著:大久保
治男 発行所:高文堂出版社 ヨリ |
| Next |