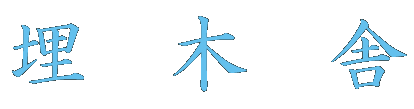大学生活二年目にはいった賀川が専攻した学課は、自然科学の分野であり、主として生物の世界だった。そのため教室で講義を聞くより、一人で博物館にこもることが多かった。後に
『立体農業の研究』 を著し、農民福音学校を通じて立体農業の普及にのりだすが、農業生産への関心を育んだのが、プリンストン大学博物館におさめられていた、生物学の文献や資料であったと言えるかもしれない。
一方、プリンストン神学校では四年かかる全課程を二年で突破し、バチュラー・オブ・ディヴィニティーの称号を授与された。皮肉にも、半分の二年間で卒業という栄誉は、奨学金の打ち切り、という苦境と引き換えであった。学資の途を絶たれては、プリンストン大学ともお別れしなければならなかった。学業半ばで大学を去る賀川に対して、
「日本人といえば、生意気なやつと決まっていたが、君はそうではなかった。
── 君と別れるのは、じつにさびしい・・・・」
色々な人種の学友たちは別れを惜しんで、様々な肌色の頬を濡らした。
「これからどうする。すぐ、日本へ帰るのかい?」
「できればシカゴ大学へ入り、哲学を勉強したい。それには学費を稼ぐ必要があるので、ニューヨークで職を探すつもりだ」
学友たちに見送られてプリンストンを後にした賀川は、ニューヨークに向かった。
不況はさらに深刻になっていた。職は無かった。八月の焼けるような暑さのなかで、コンクリート・ジャングルをさまよった。いつしか足はウオーター・ストリートに踏み込んでいた。
新川の貧民窟を思い出させる、饐えたような臭いが立ち込める町だった。黒人やユダヤ人のスラム街である。
「ねえ、あたしの体を買わない。こんなにきれいよ」
娼婦が擦り寄ってきて、スカートの裾をめくってみせる。
「おじちゃん。お花買ってよ」
裸の女の子が、花をかかえて駆け寄った。ちぢれた髪の毛の上にかさぶたが浮いている。
「かっぱらいめ!
── こんちくしょう!」
棒を振り上げた大男が、浮浪者を追いかけていく。
新川と同じ光景がくりひろげられていた。
「大阪」 の貰い子のおせいちゃんや
「喧嘩安」 などを思い出して、ぼんやいたたずんでいると、不意にあたりが騒々しくなった。海鳴りのような足音と、雷鳴のような怒号であった。広い道路を埋めた群集が、ブル街から貧民街へのりこんでくるではないか。
はじめて見る光景だった。歩道の並木にもたれて、賀川は大群衆の流れを見守った。地から湧き出たような人間の流れであった。
『われわれにパンを与えよ!』
『労働者は団結せよ!』
「資本主義を葬れ!』
プラカードが林立していた。様々な色の旗が波のようにゆらめいた。シュプレヒコールが天をゆるがせた。六万人のデモの流れだった。むくつけき胸毛のイタリア人の労働者、かぎ鼻のユダヤ人の労働者、肌の色も様々な女工たち・・・・十六列の横隊を組んで、デモの流れは通り過ぎて行く。
賀川の胸は鉄のたがでもはめられたように、重く締めつけられた。
「労働者とは、なんだ?労働者と貧民は、どこが違うんだ?労働者も失業すれば、貧民ではないか。おれはいま、その事実をこの目で見ているのだ!」
人目が無ければ、そう叫びながら、賀川は自分の胸ぐらをひっつかんで、ゆすってやりたかった。
「今までやって来た貧民救済事業だけでは、貧民の真の救済にはならないぞ。貧民問題の解決とは、労働者問題の解決のことなんだ。このたくましいエネルギーをもった労働者の救済なくして、理想社会の建設などありえない!」
賀川は職を探すのを一時放棄した。自分が食えなくても、学べなくてもいい。貧民や労働者を救う道を探すのが先決だった。その一つの方法が、アメリカのセツルメンツを調べることだと考えた。ニューヨークのセツルメンツは新川のそれとはくらぶべくもなかった。設備も組織も整っていた。日本のそれとは、天国と地獄ほどの違いがあった。しかしすばらしいセツルメントに触れても、賀川の心は晴れなかった。 |