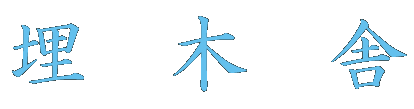やはり貧民窟の一角の吾妻通二丁目に、福音印刷会社があった。賀川がその工場へはじめて足を踏み入れたのは、明治四十四年の夏であった。
布引教会の竹内宗六牧師に連れられて印刷工場の集会所に入ると、七、八十人の男女工員が集まっていた。彼らの目は、牧師が連れてきた青年に一斉に注がれた。
青年のりりしい顔立ちに注がれた目ではなかった。裾の破れた袴と、よれよれの着物にびっくりしたのだ。きっちと分けた頭髪と、澄んだ目が泣ければ、貧民窟の大道芸人である。
紹介を受けた青年は、すっくと立った。
「わたしは新川の貧民窟に住む、乞食の親分であります」
娘たちはキャッと叫んだ。
「いいぞ、親分!」
若者たちは拍手した。
「さあ、みなさん、元気な声で歌いましょう」
オルガンが鳴ると、乞食の親分は小さな体を反り返らせて両手を振り、賛美歌の音頭をとった。 |