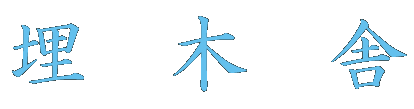きたない、恐ろしい町だった。男は好色そうな目でなめまわし、意地悪な女の目が背中に突き刺した。
四ッ辻に出た。
『神は愛也』
の赤文字の高張提灯が立っていた。人垣の中から、賀川の声がひびいている。
「神は、自分で自分を無価値な人間だと思っている人の仲にも、いらっしゃる。神は、万人のことごとくに愛を注いでくださる。神は愛であります。私たちは神の子です。私たちも、万人を愛さなければなりません」
グンシュウノ陰に隠れて芝はるは耳を澄ました。火を吐くような声が、体の中を突き抜けた。
「路傍でのお話は、ここで終わります。これからは教会でお話を続けます。聞きたいお方は、私と一緒に教会へおいで下さい」
提灯を担いで、賀川はすたすた歩きだした。何人かがうしろに従った。気づかれないように、はるはずっと離れてついていった。
その日以後、芝はるは、日曜日には貧民窟の教会へ通った。賀川の説教を聞き、賀川の近くにいるときが、はるにとっては幸福な時間になっていた。
明治が大正に改まった年のクリスマスに、賀川の教会では
<乞食招待会> が開かれた。はるは工場を休み、手伝いに行った。
ボランティアの婦人に交じって働くはるを、賀川は天幕の影からながめた。
乞食のいうままにはるは赤飯をお給仕した。汚い袂を開いて、おにぎりを入れてやった。乞食を一人前の人間として接しているはるの姿に、賀川は感動した。
──
あの娘は、乞食の心理を理解している。そうでなければ、あんなふうに振舞えない・・・・。
あるとき賀川は、鶏小屋で行き倒れていた、おみつという乞食婆さんを背負って帰ったことがある。半身不随のおみつの世話は、男世帯ではたいへんだった。賀川はもちろんのこと寄宿している男たちも、垂れ流しの尻の世話までしなければならなかった。
工場の休日だけでなく勤めがある日でも、ちょっとした暇を見つけては、はるはおみつの看病に来てくれた。
「ほら、ほら、お尻がよごれたでしょ。きれいにしましょうね」
子供をあやすように、おむつをかえ、体を拭いてやった。
二人の間には、激しい愛情が芽生えた。
大正二年五月二十二日、神戸市下山手通七丁目の神戸教会では、奇妙な結婚式が行われた。
花婿は紋付の羽織で袴をつけていたが、うしろに従う一行は、かさぶただらけの子供や、刺青男や、よぼよぼ婆さん、よぼよぼ爺さんたちだった。
花婿は山室軍平から贈られた羽織、袴をまとった賀川豊彦であり、花嫁は芝はるであった。裾模様の衣裳をまとい、束髪を結い、薄化粧した花嫁は美しかった。 |