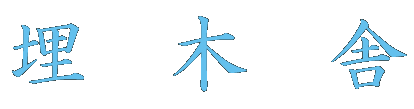二人の修験上がりは、解かれた猟犬
のように、すぐ白洲へ下りて来た。
そして、意地悪い眼と嗅覚
を働かせながら、弁慶以下十二名の偽山伏の座を、一人一人克明に睨
めまあして歩くのだった。
伊勢、片岡、亀井などの面々は、皮
剥 ぎ役のその法師が、ふと、義経の前で足を止めたときなど、思わず体を硬ばらせた。制しようもなく、研がれた眼気をつい持って、左の手を、腰の戒刀
へ忍ばせた。
もし、皮剥ぎの役の彼らが、ひと言でも、主君義経を、その人と、看破
するかのようだったら、二言と言わさず、すぐ起って斬り伏せてしまおう。また、吟味の席にある富樫左衛門尉をも刺し殺して、一挙に、関を踏み破らん。 ── 伊勢、片岡ばかりでなく、その覚悟は、ここの関所へかかる前から、既に一同の中で、申し合わせていたことなのである。
──
が、体も小柄なうえ、旅の垢
にもまみれて、さも疲れたように、踞
っていた末弟の一山伏を、彼らも、さすがにそれとは、疑いきれなかったものらしい。
皮剥ぎ役の法師は、義経へ注いでいた眼を、ふと逸らすと、急に弁慶の方をあごで指し合いながら、列の首
めの所へ戻ってしまった。
正面の階
をはさんで、弁慶と向かいあいに、彼らもそこで、重々しげに床几
へ腰かけた。真の山伏か偽山伏かを、試むための問答を、職としている修験上がりの彼らなのだ。おそらく、弁舌や博識は、みずからも充分、誇るところががあるに違いない
「まず、もの申すが」
と、弁慶を正視しながら、問答坊しての一人が、まず口を開いた。
「客僧がたの中でも、わけて貴僧は、大峰に入ること三度、白山、羽黒にも、修行を積んだ大
先達 とのこと、それほどな行者とあれば、修験道
百般、何事にも通じておらるるものと思うが」
「いやいやなんの」
弁慶はうす笑って、
「道の深遠
、虚空 の大
。 ── 百事に通じるなどとは、凡身一生をかけても、足らぬほどな悲願ででおざる。なれど、知る限りは、お答え申さん。なんなりと、問い給え」
「ならば、問うが、優婆
塞 の起こりは」
「役
の小角 を、祖といたすは、人も知ること」
「教義は」
「自
行 自
受 。 ── 身をもっていたす実習実行こそが、即
、教えでおざる。ゆえに、他宗門のごとき、宗祖はない。深山大岳を、道場とし、法耳
をもって、大自然に法 を聴き、法心を研
いて、石の声、渓 の水にも、道を聴く」
「その、願うところとは?」
「即身
即仏 」
「とだけでは、明らかでないが」
「生仏
不二 。 ── その身そのまま、現前に、仏果の証
を、この肉身に知ることに他ならぬ。」
「そは、天台、真言も説き古
したこと。事新しい儀ではあるまい」
「されば、小角
の後、五大山伏と仰がるる大
先達 がおわす。 ──
智証 、理源
の両大師、また、白河院の増誉
など、それぞれ、山林苦行の験を身をもって示され、熊野、大峰、葛城
の諸山に壇を開き給う。 ── それより、風
を慕うの輩 、たとえ出家の身で非
ずとも、在家 、蓄髪
、妻帯のまま、みな現前の証得
に逢 わんと願うて、修験
の道に入り申したり。・・・・ゆえにそれ、修験の道の、いやちこなる功徳
いかんといえば、天地の大自然を師壇となし、農は農のまま、士は士のまま、生身
に即仏 の歓
びを知ることかと覚えて候う」
「では、その持仏
は」
「大日如来、まった、普賢
、文珠 、不動
、弥勒 、観世
音 の諸
菩薩 をあがめ奉る」
「あがむる仏
も、他宗とたがわず、求むる願いも、変わりなきに、その行儀、修法に相違あるは、いかに」
「峰中の修行、大岳の起臥
。おのずから伽藍 の行儀衣体
とは、違うが自然と思わるる」
「聞き及ぶ、それらの十六道具とは」
「兜巾
、斑蓋 、篠懸
、袈裟 、法螺
、念珠 、錫杖
、笈 、肩箱、雨皮
、脚絆 、引敷を十二道具ととなえ、また檜扇
、柴打 (戒刀、あるいは斧
) 、走り縄
、草鞋 を加えて、十六道具とは申すなれ」
「兜巾
の布は五尺と聞く、五尺の意
は」
「五智 の宝冠を象
るとか」
「十二の襞
は」
「十二因縁
を折りて、頂く」
「篠懸
とは」
「九会 曼
陀羅 の象徴
と申せど、これはただ、山路の篠
に懸ければの名か」
「法螺
の貝は」
「迷霧
の道しるべ、あるいは、法会
の式具に」
「してまた、八ツ緒
の草鞋 は」
たたみかけると、弁慶は、とつぜん、両の肩をゆすぶって、
「あら、ばかばかしき物問いかな」
癇癪
の疼 きを、歯の根に怺
えて、あざ笑った。
「── そも、八ツ目の草鞋は、八葉
の蓮華 を象
るぐらいなことは、山伏の初学。あれ、あの末座の法弟どもさえ、心得おるところだわ。さるを、いちいち博識ぶっての物問いこそ、笑止なれ・。・・・・いかに富樫どの」
と、その眼を、正面の泰家へ移して、
「げに愚
かな日長問答。かかる愚弁を聞き居給うは、富樫どのにも、さだめしお欠伸
を催 されん。貧道
ら一同にとっても、じつもって迷惑千万。このうえは、疾
う疾 う、関の木戸を押っ開いて、お通しあらんことを希
う。お約束のごとく、お通し給われい」
と、いっそう声を大にして、どなった。
すると、富樫泰家が、何も言わぬ先に、もう一人の問答坊が、
「いやまだ、そうはならん」
食って懸かるように、弁慶へ向かって吠えた。 |