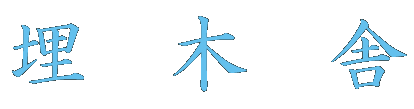「── およそ、かくれないことでおざれば、ここの富樫殿にも、夙
に、御存知はあらんも、一応は申し奉らん。かねて、南都東大寺大仏殿の建立
にあてって、ひろく世間に結縁
を求めんため、大勧進の智識重源
上人 には、一輪車
六輌 を造って、老躯
をはげまし、七道諸国を、数年にわたって、説き歩き給う」
流れるような声である。
弁慶は、間
を置いて、
「されば、われら修験の輩
へも、造 東大寺大仏使より切に合力を請い求めらる。もとより一世の所願
なれば、吉野、葛城
はいうに及ばず、全土全山の優婆
塞 をあげて、こたえ奉らんの約を結ぶ者、数百。
── すなわち、貧道
らは、奥羽を巡行して、人びとの報謝
を仰ぎ、あまねく、仏果
を得せしめんがために、かくは多くの同行を具
して、まかり下る。・・・・しかるに」
一歩、階の方へ進んだ。
蛇
の目が、はっと、動く。
泰家は、まじろぎもせず、弁慶の唇
もとを見ていた。
「いかなるわけか、この関にては、修験者とだに見れば、ただの野伏
りか盗賊かの如く、まず邪悪視して、いささかの疑点あるも、ただちに、獄へ投じ給うかのういわさを聞く。・・・・まことにもって、言語道断、富樫殿ともあろう御守護が、さる悪政を好ませ給うはずはない。貧道らは、以上述ぶるところの所願のため、遍歴いたす者、願わくば、一刻
も早く、関をお通し給わらんことを。 ── 併
せて、かかる直面 を仰ぎえたるも、また一つの法縁にこそ。たとえ、なにがしかの宝財なりとも、勧進の内へ、喜捨あらせ給わば、ありがたく存じ奉りまする」
一気に言い終わって、弁慶は、指に懸けていた数珠
の手を胸に合わせて拝 をした。
「む、あきらかな返答。その儀は、よくわかった」
と、泰家はかろく、
「したが、かくれもないことというなれば、ただ東大寺大勧進の触れのみではあるまい。去年
より四たびの院宣さえ降って、鎌倉どのが、諸州に追捕
を令しおかるる叛賊義経の沙汰もまた、三歳の児童も知るところ。御僧
たちとて、それを知らないでどうしよう」
と、薄く笑ってみせた。
ぎくと、こたえながらも、弁慶は。
「あいや、前
予州 どのの追捕沙汰なら、わきまえぬとは申しませぬ」
「ならば、いずこの関といえ、いとど検
めのきびしいは、知れたこと。わけて、判官主従、偽
山伏となって、国々を潜み歩くとの風聞もある。聞き及ばぬか、そのことは」
「そは、きつい迷惑に存じおりまする。聖道を行くわれらにとっては、憎
んでも余りある似 而非
行者 。もし見つけたら、容赦はなりませぬものを」
「それよ、まして、鎌倉殿の厳命の下に、ここの関を守る富樫左衛門尉ぞ。たとえ、東大寺直々
の勧進僧たりとも、やわか、糺
さずに通そうか」
「なおまだ、なんの御不審やわる?」
「不審は」
ふと、泰家は、弁慶から視線を逸
らした。
彼以下の、平修験者の座列を、そして、その一つ一つの面
魂 を、ずうっと、ながめてでもゆくような眸だった。
弁慶は、胸騒ぎを、制しきれない。
──
義経が、どうしているかを、背だけで、案じた。
泰家は、またいつか、その弁慶の面
へ、しずかな眸を戻していた。
「先達
の俊乗とやら。なお解けぬ疑いは、にわかにも挙げきれぬ。吟味は、これからぞ」
「あら、言語道断、迷惑な長吟味よ。何をもって」
「だまれ」
泰家の、大喝
は、彼の侍臣や、白州の番将さえ、驚かせた。
「世事にうとき山伏と思い、申すがままに、よう扱ってつかわせば、守護をも、関をも恐れぬ雑言
。言葉の端にも、腑 に落ちぬものがある。
── 種次っ」
番将の方を望んで。
「白洲のめぐり、木戸の外、兵どもに取り囲ませて、この山伏どもを、びくとも起たすな」
「はっ、油断はございませぬ」
「よし」
面を横に向け直した。そして、さっきから、彼の側にあって、猜疑
の目をとぎすましていた修験上がりの法師二人を見て、こう、いいつけた。
「下へ降りて、その方どもから、勧進の実否、行道
の百般、仮借 なく、問答をこころみてみよ。左衛門尉の前に出て、思うざまな下の根をいふるい、倣岸
、かくの如きは、まだ見たことがない。偽
山伏 にせよ、なかなかのやつと見ゆるぞ。見事、こやつらの面皮
を引っ剥 いで見せい」 |