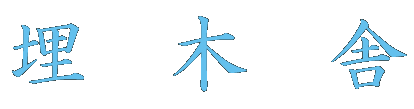加賀の守護、富樫泰家は、まだ四十がらみか。地方の守護としては、若い方である。
父家経、兄家直の跡をうけ、家督
をついでからも、まだ、七、八年しかたっていない。その間には、かの木曾上洛があった。彼は、義仲の軍に加わって平家を追い、ともに都へ出た。
が、まもなく、彼は郷里野々市へ帰って、引き籠ってしまった。木曾兵の暴状にあいそをつかしたのである。若い理想は、懐疑に落ちた。のみならず、木曾の荷担
人 たるかどで、長い謹慎が門に続いた。
古い加賀の名族。
祖先は禁裡
の滝口 に候
し、鳥羽 殿
建立 にも功もあったりして、地方ではゆゆしい六位の介
でもあった。その名門を、自分の代で、傷つけた自責なんどか、あるいは、木曾軍に従って、広い世の中の実態を見てからの懐疑の末だろうか。
「あれからは、お人が違いなされた」
と、周囲によくいわれたりすた泰家だった。そして、この国では、
「野々市では、まれに、唖
が物仰る」 とか、 「偽唖
が物いうたら恐い」 などという言葉すら行われた。それほどに、泰家は無口だった。
左衛門尉を兼ねて、加賀の守護に任ぜられたのは、つい去年の春である。
そのため、彼は、鎌倉の府へ、お礼に赴
いた。蔭で推挙の労をとってくれたという梶原景時への許へも、挨拶にまわった。
梶原の息子の景家
たちに誘われて、一夜、安達新三郎の邸へ、遊びに立ち寄ったのも、そのおりのことである。しかし、
「つい、見まじきものを見た」
と、その夜の出来事は、後々まで、彼の後悔となっていた。
ちょうど、安達の邸には、義経の愛妾
静 が預けられており、景家らの心は、その幽囚
中の麗人を、酒興にして遊ぼうという魂胆
であったのだ。
泰家には到底、愉
しめることではなかった。そういうものを見て愉しめる人間の気が知れない。
不愉快だった。 ── という以上、その夜の、若い御家人どものざまに、彼は、ひそかな義憤すら抱いた。
また、新幕府を支える若い層そのものにも失望した。以来、
「唖ならぬ富樫どの」 は、帰国後も、唖でない証拠ぐらいにしか、ものを言わない人で今日にいたっている。けれど、領下はよく治まっていて、
「良い、御守護」
という領民の声は、弁慶たちも、途上、たびたび耳にしたところだった。
だから、この関所へかかるにも義経始め、富樫その人が、どんな人物か、器量のほどを、あらかじめ推
し測ることもむずかしかった。
なんの成算もなく、ただ、 「当たって砕けろ」 の覚悟で、直面したまでだった。
が今、見ても。
一見して知れるような泰家ではない。
しごく凡庸
な常識家かとも見えるし、炯眼
、油断のならぬ沈剛
な人かとも、惑わせられる。清酒
な狩衣 、大口
袴 、烏帽子
という姿は、いたずらに、威を飾っているのでのない。
ただ、今日の吟味には、どかっと、腰をすえているらしい容子は、確かに見える。
色の浅黒い、そして。眉から鼻梁
の辺にも、北国の名族らしい気品を備えた面に、それが、ほの紅い意志の色を呈していた。
弁慶は、見てとって、内心 「── これは安からず、たやすくは、騙
りえまい」 と、ひそかな腹をかためずにいられなかった。
そこへ、床几
や、莚 を皆へ頒
って、番将の種次が、一同へ、
「いつにない、お扱いぞ。先達は、床几につかれい」
「かたじけのう存ずる」
弁慶、承意、仲教の三人は床几に、あとの面々は、おのおの金剛杖
を横に、むしろの上へあぐらをくんだ。
まず、弁解は床上に一礼して、
「かく、お扱いを賜るうえは、なんなりと、御法に順
って、神妙にお答え仕らん。先を急ぐ旅には候わねど、陽も高きうちに、手取川までは参りとう存ずる。いざ、御吟味を」
と催促した。
泰家は、うなずきを見せた。
「まず問うが、方々
は、いずこの優婆 塞
なるか」
「常住
の地を問い給うか。われら修験には、定まれる家とて、おざらぬ。およそ天下の山沢大川、人なき雲表
といえ、つえの立つ所をもって家となす者。 ── なれど、里には、座主
先達 の院家
、役室、諸房もあって、われらは大和葛城
に僧籍をおき、大峰にはいること三度、白山、羽黒にも修行を経たる先達
にござりまする」
「御僧の、名は」
弁慶は、待っていたものを、吐くように、
「熊野坊俊乗と申す者」
と、すぐ答えた。
熊野は、彼自身の郷地、俊乗は口から出たままの仮名である。
すぐ、言葉を続けて、
「このたびの同行には、われら先達三名のほか、以下の平
修験 ども、十名を連れておりまする。これなるは呵雲
坊 、次なるは無憂坊と申す。
── そのほか、順に名のらせましょうや」
「いや」
泰家は、さえぎった。
「いちいち及ぶまい。まず、先達三名に、物申そう。見うけるところ、強力
、童 まで連れて、いと大形
なる旅の様、そも、いずこへ行かれるか」
「よくぞお訊
ねを。 ── それこそ、お訊ねなくとも、われより申し上げたい一儀にて候う。じつは」
弁慶はぬっと立って、泰家の座へ、その巨きな胸板を真向かいにした。
泰家も、きっと眉を澄ました。
けれど、弁慶を射た鋭い視線は、泰家の眼光ではなく、彼に侍座していた僧形二人のものであった。それは、木蔭の蛇
が餌 に向かって吐く妖気
みたいなものを感じさせた。
弁慶は、思い当たった。かねて聞いていた里のうわさを。
関所には、修験者上がりの、二人の法師が抱えられている。山伏の吟味には必ず立ち会う。そして難問難題をわざと出して、偽
山伏か否かを、こころみる。もし、それに答えられぬか、無学や未熟の皮を剥がれると、仮借
なく、獄へ下げてしまいことをである。
── ははあ、その皮
剥 ぎ法師だな。
眼のすみから、一瞥
をくれて、弁慶は、おもむろに、口を開いた。 |