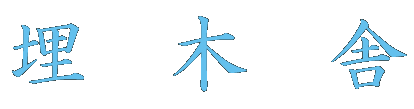遠見の番卒は、すぐ、下の番卒へ、
「あれよ、物々しい山伏の一群が、これへさしかかれうぞ」
と、告げていたに違いない。
早くも、その物々しさは、彼らの中に見えて、道に立ちはだかっていた。
弁慶は、同行
を後ろにおいて、ただ一人、ずかずかと、その前へ進んで行った。何やら呶々
と説明に努め始める。持ち前の音声
と六尺の背丈は、それだけでも、相手を慴伏
させるに充分だった。番卒たちは、初めの気勢も失せ、ただ気圧
された沈黙にまじまじしていた。
そのうちに、弁慶が、片手を振って、振り向いた。 ── 後ろで、固唾
をのんでいた面々へ、目配せをしたのである。
「よいそうだ、よいというわ、通り候え、人びと」
番卒たちは、あわてて、
「よいとはいわぬ」
「やあ待て。修験衆」
にわかに、わめいたが、弁慶の大またな歩みにならって、一同もまた、どやどや橋を押し渡った。
そのどれ一人、凡物
とは見えなかった。ひと癖ありげでない者はない。番卒にも、はっと、眼に映ったものだろう。手出しはし得なかったまでのこと。関門
へ向かって、ばらっと二、三名は先に馳け出し、また例の、貝の音
が、鳴り渡っていた。
関門までは、わずか数百歩。
柵
に、幕を打ちめぐらし、門の内側に二ノ番所、横に関所館
や厩 が見える。
すると内から、番将の一人が躍り出て、何か辺りへ高々と怒鳴っていた。
「── 出合え、出合えっ」 とでも叫んでいたらしい。たちどころに、無慮五十名ほどな兵が起
って、陣を作 した。末端の兵は、弓弦
に矢つがえした。もう、眼前へ来ていた山伏の一群を睨
まえてである。
「やあ、ひかえろっ。そこで待て」
番卒はしかった。まるっこい巨きな体が振りしぼった声なのだ。
「ここを、どこと思う。富樫殿がかたむる安宅ノ関、なぜ、番卒の命を待たず、無法に押し通るか」
「これは関守
のお役方にて候うか。先達
として、一同に代わり、お答え仕る」
叡山の承意が前へ出て、いんぎんに色代
(あいさつ) していう。
「名だたるおん関所、なんで、無下
な振る舞いに及びましょうや。これなる同朋
が、早呑み込みに、委細のお調べは、御関所と指さすまま、一同、わきまえもなく、通ったまでにどざりまする」
「ようし、それが真実か嘘
か、急には、問うまい。眼に余る同勢、一々念入りに検
めてやる」
番将は、かたわらの者へ、耳打ちして、どこかへ走らせ、そしてまた、言い続けた。
「およそ近ごろ、修験往来の徒には、とりわけ、関の吟味のやかましいことは、里々
のうわさにも、聞き及んでおろうがな」
「もとより、この人数のこと、疚しからねばこそ、かようには、白昼、おおらかに、歩んでおりまする」
「むむ。広言はなんとでも吟味所で述べろ。そのまま、一名残らず、あれなる内へはいれ」
番将は、南側の関屋の柵
を指さした。
そこにも、別な木戸が見える。
「番卒ども、修験衆を、吟味所へ」
彼の言下に、兵は、義経主従を取り囲んで、うむをいわせず、柵内へ追っ立てる。
内は、ただ玉砂利が敷きつめてあるだけの広い庭だった。関屋の廊は鍵形
に白州 を抱えて、正面の階
の上には、広床 が見え、まだ真新しい木の香がつよく鼻を摶
つ。
「下におれっ。なぜ、下に坐
かぬか」
番将が、しきりに、叱咤
するのを、
「心得ぬことをば」
と、弁慶は、小うるさ気に、
「われらは、ただの往来人、なんで、白州に伏さねばならぬいわれがあろう。つねに大峰、葛城
の行場 へこもって、身を滝
津瀬 に打たせ、かりそめにも、不浄を厭
む優婆 塞
の弟子でおざる。 ── すわれと仰せなら、すわりもせん。だが、広床に座を賜るか、一同へ、床几
をお与え給われい」
いい払って、彼以下も、突っ立ったままでいた。
すると、正面の床上
に、侍臣数名、法衣ていの者二名を、左右において、じっと見ていた眸が、
「種次
。先達 には床几を与えろ、その余の者へも、菅莚
をやるがいい」
と、下の番将へ、しずかに命じた。
富樫左衛門泰家は、その者だなと、弁慶は、心のうちでうなずいた。
泰家の眼と、弁慶の眼とは、もう、無言のうちに、相摶
っていた。 |