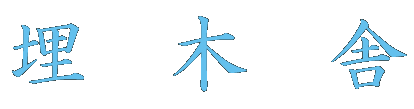── 草の間を縫う水たまりは温
かった。目高か何かが泳いでいる。
だが、子供らは、もっと水の冷たい早瀬に群れて、錆
びた兜 の鉢金
や太刀の鍔 やらを、鵜
の目 で、探しあっていた。
春の加茂川から、どうかすると、金
が拾えると言われている。保元、平治、木曾合戦、いろんな時に、ここへは武者の打ち物や屍
が流れがよどむほど水漬
いた。今も何かが砂礫
の下からキラと出ないとは限らない。
それよりは、ここに遊んでいる七ツ八ツから十がらみの子どもは、この川を赤くした血の色を見ず、矢叫
びも知らずに育った。
つい、二、三日前、この河べりの、大きな紺
掻 き
(染物屋) の干し場へ来ていた麻鳥は、それを眺めて、
「ああ、義経の君へ、お見せしたい。・・・・思うても愚痴だが、あの童たちの平和な姿を御
覧 じあれば、さぞ御本望であろうものを」
と、ひとり涙ぐんで帰った。
紺掻きの鵜八
の家の広場では、河原へかけて、張物や、紺掻きや、布晒しなどに立ち働く男女の姿が大勢見えた。 ── 麻鳥の息子の麻丸も、今では、ここの染工の一人だった。まじめで、機転がよく、無類に働くので、親方の鵜八も、
「はやく、よい女房でも持たせたいな。今に、よい紺掻きになるで」
と、たれへも言っている。
だが、その真面目
さを、なかなかほんとにしないのは、他人ではなく、当人の親たちであるらしい。麻鳥夫婦は、おりおりここへ来ては、
「なんとか、やっておりますか」
と、鵜八へ訊いては、帰ってゆく。
常陸
の勿来 まで行って、金を使ったお蔭で、あのさい、麻丸以下の、首だけは、つなぎとめた。けれど、関所の獄に、三年の刑は命ぜられた。それをまた、おととしごろ、迎えに行き、やっと、親の許へ、連れ帰って来たのであった。
──
そうした極道 な、経歴を持つ麻丸も、はや二十七、八である。別な意味では、親の麻丸以上、子どもではない。博打、女道楽、悪事の数々、下層社会の暗闇のことなら何でも知る尽くしていよう。それを親たちがまだ不安がって、むかしなみに、意見でもすると
「・・・・・・」 ニヤリとただ笑って見せるのだった。その無口な顔のうちに、きのうまでの悪の体験が、どう、別な根性となって包まれているのか。親たちにも、読み切れないのである。
── むしろ、そこは他人の鵜八の方が、はるかに、彼を信用していた。
「おい、麻丸。一休みしないか。手でも洗って、ちょっと、こっちへ来な」
「いけませんよ、紅花
はむずかしいから、こいつを絞り上げてからにしましょう」
「まあいい。他にも話があるんだから」
鵜八は、彼を住居の下屋へ連れて行って、
「文覚さまが、佐渡でお亡
くなりになったとさ」
「へえ、島流しになると騒いだのは、つい去年ごろのことでしたのにね」
「お年もお年だ、佐渡ケ島と」きちゃあ、お体にも、こたえたのだろう。だが、島では、絶食して、入寂
されたとか、たった今、高雄のお使いが見えて、聞いたんだが」
「どんな人間でも、年をとると、やっぱり、人は死ぬもんなんですね・・・・」
「当たり前だわな。はははは、何しても、おれの兄五郎次とともに、兄弟の大恩人だ。また麻鳥どのとも、容易な仲ではない。汝
れやあ、家へ帰って、さっそく、親御たちへ、このことを、知らせてくれ」
島から遺骨を持ち帰った弟子僧があり、高雄神護寺では、勅勘
のみゆるしなくもと、内々通夜
葬儀の営みを行うことを決め、ごく深い縁故者だけへ、密
かに会葬触れをまわしているというのである。
麻丸は、急いで、わが家へ帰った。 |