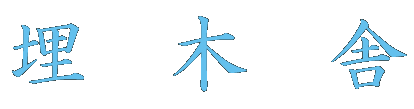ほどなく、一人の老尼が、そこを開けて、外の人々を見るやいなや 「・・・・あ?」 と、驚きしびれたように、ひざまずいた。
後白河は、老尼の背へ、眸
を落として、
「はて、見たような?」
と、小首を傾
げて、仰った。
尼は、しばらくの間、御返事にも及ばず、とっさの驚きから醒
めたあとも、さめざめと泣き暮れていたが、ややあって畏る畏
るお答えした。
「あまりに年月も経
、姿も変わり果てましたゆえ、御覧
じ忘れあそばすも、ご無理ではございませぬ。わたくしは、故
少納言 信西
のむすめ、阿波 ノ内侍
と申しまする。母は、紀伊ノ二位ノ局」
「おお、紀伊のむすめか」
後白河は、もういちど、おん眼をみはられた。自分の乳母
のむすめが、もうこんなにも、年老いていたのか ── と、そぞろわが身に過ぎた歳月も、振り返られたものであとう。
「・・・・女院は」
と、お問いになると、
「この上ノ山へ、花など摘
みにと、、今し方、お出ましなされました。さても、おもいがけない御幸、夢でございますまいか」
と、内侍は、信じられぬことに直面したように、おろおろしつつも、すぐ山の方へ、告げに行こうとした。
後白河は、内侍をお止めになって、
「さは、驚かさぬがよい。しばらくは、まろも山路の疲れを、かなたで休めていようほどに」
と、主
の見えぬ御 庵室
へ通られた。
内侍は、障子を引き開けて、卯月 (四月) も末の翠光
水声 を、隈
なく呼び入れ、池水に咲く紫や、籬
のつつじ、山吹、山藤
、雪柳など、唐 屏風
の絵のようなながめを、叡覧
に展 いた。
「オオ木立の様、閑居の清らけさ、寺房は寺房の山水
ではあるが、さすがどこやら女性
の住まう趣 なある」
と、法王は、それも御感
の態であった。がなお、おん眼を凝らされたのは、朝暮
、女院が平家一門の供養と、世の泰平を、御祈願あらせられるらしい、お勤めの座であった。
正面に、三尊
の像をおかれ、中の釈尊
のお手には、五色 の糸が懸けられてある。
── いつ死なんとも、来世
のみちびきは、まかせ奉らんと願う、引導
の糸、誓いの糸とみえる。
方丈窓の下を見れば、そこの小机には、法華経、九帖の経巻などが、おかれてある。
しかし歌書はあっても、反古
の乱れは見えず、塵 だにない冷たさは、余りに世の外の物のようで、酷
いばかりな厳 しさと、あわれを、ひしと感ぜしめる。
また、ほの暗い、次の小間には、御寝所か。
荒壁へ寄せて、竹の竿
の衣桁 に、麻のおん衣、紙の衾
などが、懸けてあり、おん袖に、青い虫が一匹、ひげをふるわせていた。ほかにといって、何一つない。 ── かっての日には、唐衣
や袿衣 の袖に、幾重の色を襲
ね、綾羅 の粧い、錦繍
の妍 を競い合う、宮中の麗人たちの中にいてさえ、いつ、どんな所でも、見劣ったことのない建礼門院の、これが今は、御起居の物の、すべてであろうか。
「・・・・・・・」
法王は、触目の一つ一つに、お心を涙で刺されずにはいられなかった。治承、寿永このかた、いやそれより以前から、このような生贄
を、乱世の血の祭壇と魔神の前に、どれほど捧げて来たことであろうか。
ふと、御感慨もわく。
けれど、その乱世の雲の上に坐して、御自身が、どう処
されて来たか、清盛をして、 「後白河の君こそ、希代
な政略家なれ」 と叫ばしめ、また、頼朝をしてさえ、 「大天狗とは院のことなり」 と言わしめた、御自身の内にあるもの、それへの御反省までは、思い及ばれもしなかった。
ただ、かえりみれば。
平治から幾十年のうちに、御血縁の皇族、寵臣
、外戚 の平家、そのほか、無数の武者輩
まで、戦い戦い、ほとんどみな落花か血の泡沫
とかき消えてしまったのに、御自身のみは、ひとり帝王の座も失われず、六十のおん齢
もなお矍鑠 として、こう在ることが、極めて当然な、としていらっしゃる君王の常識のうちにも、多少、他への憐
れを、お催しにはなるのであろう。わけて、亡
き御実子高倉帝のお后
であり、清盛の一女であった女院へは、とりわけ、御
憐愍 の切なるものがあったには違いない。
──
山へ花摘みに行かれたという女院はまだお姿をみせなかった。が、後白河は倦
むこともなかった。
何か、今日一日だけは、人界を離れて、人界の古往
今来 、さまざまを、思い巡らすため、ここに置かれた様な心地でもある。
そにうちに。
── ふと後白河は、たれかの眼が、ここの自分を、さっきからじっと見ていたことに気づかれた。それは、横の、ほの暗い壁に懸かっていた一
軸 の童子像であった。
たれの筆に成ったのか、画像は、まぎれもない先帝
(安徳天皇) の御影
である。おん母の手で、今も朝夕、欠かすことなく、上げられているのであろう。供御
の膳器 、花、香炉
などが供えてあった。
後白河は、その似絵の眼と、御自分の眼が、ゆくりなく、出合ったような気はされたが、実の御孫にたいする愛撫
の情はわいても来なかった。かえって、何か、背すじへ寒さをお覚えになったらしく、あわてて、お眸を、外へそらした。
ちょうどその時、裏山からの小道を、ここへ降りて来る二人の尼僧が、かなたに見えた。よくよく御覧
じあると、濃い墨染めの法衣
、ま白な下重ね、ふと見違えられもするが、先帝の乳人
大納言佐ノ局
と、もう一と方は、まぎれもなく、後白河が、待ち久しげにお待ちしていた建礼門院に違いなかった。 |