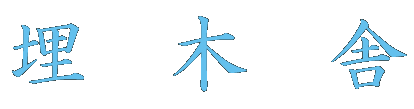佐
ノ局 は、柴木
に蕨 を束
ねて持ち、女院は、花籠
を左の臂 に、懸けておられた。
籠の底には、山の幸を、何かと摘み入れ、岩つつじの花も折り添えてある。
── まだ何も、お気づきないのか、岩根の春蘭
に、お裾を弄 らせながら、庵室
の裏垣 までは、無心に降りて来られたようだった。
──
が、にわかに、はたと足をお止めになった。いや、立ちすくまれたお姿だった。
玲瓏
としかいいようのないお顔には、一瞬ほのかな紅
がさっと通った。
「・・・・?」
お驚きと疑いのそれが、徐々にお顔の上から醒
めて、白蓮 を思わす白さに返ると、やがてその頬を、珠
のようなおん涙が、らんかんとして流れくだっていた。 ── ぬぐうことも、隠すすべも、お忘れになっている。喪神そのものの御手に、花籠の花だけが、かすかにふるえていた。
「御幸にござりまする。院でいらせられます。・・・・女院さま」
かたわらから、阿波
ノ局 が、小声で告げる。
女院は、局の手へ、黙って花籠を預けた。そしてすぐ、頽
れるようにすわりかけるのを、簀
の子 や庭面に控えていた後德大寺、冷泉、花山院、そのほかの諸卿が、宮階でおん裳
を捧 るときのような礼で、しいて御庵室の内へ迎え上げた。
「・・・・・・」
相見たものの、しばらくは、後白河にも、おことばはない。
どんな言も、女院の今の境遇をなぐさめるには、余りに空々
しく、似つかわしくなく、ついお口にも出ないのではなかったか。
人生の流転
無窮 。
欲界の栄枯さまざま。
喜見
城 の歓楽も、長くはなく、天人にも、五衰
の悲しみとかがあるという。
仏典や経文は、星ほどな字数をもって、世の必然と、人間の業の結果を、予言もし、教えてもいる。
後白河も、それらの聖教は、ひとかどの碩学
以上にも、暗誦 んじておいでだった。けれど野の露は、どれほど沢山の露の玉であっても、花を濡らし、花を息づかせるだけで、花の生命そのももではない。
御自身、法体
にくるまれつつも、源平血みどろの者を、両の手綱に使い分け、飢餓、疫病、火災、水害の泥海にあえぐ四民の上に高御蔵
を置いて、老いも知らず、なお鎌倉幕府とも闘わんとしておいでになるほど、非凡な大俗をもって、自ら任じていらっしゃるのだ。仏教の功力
も、救い難い人間性も、お分りでないはずはなかった。
だから、女院に対しても、あきらめの日々と、往生来迎の日を愉しみ給えというような、善
智 識
ぶりを、さりげないお顔で語ろうとというお気持ちにはなれなかったことであろう。 ── むしろ、世俗の嫁
舅 の気安さで、この寒室の起居を見舞い、土産物など繰り広げて、力づけたり、慰めもして、御還幸あらんというのが、偽らないお心であったかと思われる。
やがて、四方
山 話に解けて、
「日ごろ、訪
う者は?」
と、お聞きになったり、また、
「冬の寒さ、夏のしのぎ、この山里では、さこそままなるまい。四時のお暮らし向きなどは、どうしておらるるや」
などのお訊
ねが出たのも、それのお宥
りやらお気持ちのあらわれの、ほかではあるまい。
ようやく、女院も、時ならぬお驚きから、われに返って、おりには、法王のお言葉にも、御微笑を見交わされた。
── おん年三十、ほほ笑まれれば、たちまち、黒髪に黄金
の釵子 、翡翠
の鏤 めをしておわした日の翳
が、陽炎 のように、素顔の眉やお唇
のあたりに揺らぎこぼれて、仏華
の薫染 しかないお襟もとからも、ほのあたたかい何かが匂い立つようであった。
「・・・・まこと、吉田からこれへ来た当座は、心細さ、いいようもありませんでした。たそがれ、人や来ると、さしのぞけば、鹿
の親子が、歩むのでした。夜半の嵐かと、耳澄ませば、猿
のさけびです。けれど、七条どのの北ノ方や、隆房
卿 のお内からも、お心こめて、おりおりの布施
や育 みを賜りますので、生きるに物欠くこともございませぬ。・・・・そして、ひたすらに、一門の菩提
を念じ、草を摘み、花を友に、いつか山家
にも住み馴 れたせいでしょうか。今は、僥
せな身と、この閑居さえ、勿体
のう存じおりまする」
「とは申せ、煩悩
、脱け難いは、人なみの相
、おりには、世への恨みもおわそう。過ぎし日の、あれやこれ、ひとり悲しゅう、思い出らるることもあろうに」
「仰せまでもございませぬ。けれど、きのうの悲運が、み仏への、きょうの機縁を、めぐみ給うたものと、それがありがたいのでございます。過ぎし日の飾りは、今何一つございません。けれど、ある日はふと、ああこれがわが身というものであったのか、生きの命とは、これであったかと、ひとりこの身を抱き愛
しむような日もありまする。・・・・ただただ、いつまでも、忘れ得ないのは、先帝 (安德) の、おいたわしさやら、面影ではございますが」
先帝の話になると、後白河は、何も仰らない。さすが、おつらいのであろう。み気色も沈まれた。
ほんとのところ、安德帝の御入水は、いまもって、確認されていなかった。当時、御
遺 骸
や御遺物なども海底から探りえず、すでに壇ノ浦以後、一年の余りも過ぎているが、帝は、絶海の孤島にいらっしゃるとか、山また山の奥に、小天地を作っておいでになるとか、異説風聞、南の風が吹くたびに聞こえて来る。
「・・・・おお、いつか、陽
も傾きそめました。おん物語も尽きますまいが、はや御
還御 あらせられては」
簀
の子
(縁 )
の端から、後德大寺実定が、内へ奏した。
それを機
に、法王は、小筥 の香木
“無 憂
華 ” をお袖裏から取り出して、女院へ、おみやげにと披露された。
女院は、その薫を抱きしめると、白いおん頸
をふるわせた。そしてついには、堪え難くなられたか、がばと、泣き伏してしまわれた。父の面影の香が、とつぜん、女院を幼子
に引き戻していたのである。
同時に、供奉の人びとは、おん輿
を、門べにすえて、待ち控えた。 ── 後白河は、御座
をお立ちになった。山里の入日は早く、御
庵室 の中は、もうほの青い夕冷えだった。 |