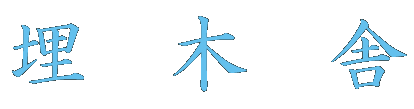牛車は、みぞろ池の北、幡枝
御堂 につないで、北面三人だけを留め、法王は、そこから先、あじろの輿
に乗り換えられた。
もう車は行きえない。道は岩倉山と神山
のあいだを縫い、ようやく山坂の嶮
をあらわしてくる。
「はや、道のりは、半ばを来たか」
山中なので、輿
の簾 を揚げ、後白河は時々、扈従
のうえへ、話しかけた。
老いたるは、輿
でお供に続き、若い堂上人
はみな歩いた。輿上
に揺られるのと、歩行とでは、どっちが楽かわからないほどである。
「いや、半ばを過ぎましても、道の険しさは、これから先だそうでございまする」
「たれかの答えを、お耳でうなずくと、
「・・・・むむ、そうだったのう」
と、つぶやかれた。
後白河にはこに山道が、今日初めてではないらしい。
が、ゆくりない御記憶が滲
み出るのを、打ち消そうとでもなさるように、ふとおひざの上の指先で、香筥
の紐を解き始めた。そして、その小さい筥
の底をお鼻のさきへ持ってゆかれた。そして 「・・・・清盛の匂
いがする」 ── と、すぐお感じになった。三寸ほど裁
ち断 った香木
が、中にくるまれてあるのだった。
名香であった。
おそらく清盛が、その晩年、宋
との交易で購 い入れた物の一つであろう。みずから、“無
憂 華
” と銘じて、福原の雪ノ御所でも、西八条の起居にも、衣に焚
きしめて、またなく愛用していた。それの薫気
の気 だかさから、内々法王にも、御所望の切なるものがあった。と知ると清盛は、秘蔵の宝木
を、惜しげもなく二つに裁
って、その一つを院へ献じたのであった。
今となってみれば、それは、清盛の気心をよく現した形見でもあり、いわば清盛の遺薫
そのものであった。 ── けれど後白河は、清盛の亡後、なんとなく “無
憂 華
” の香気に焚き染められるのが、お苦しくなった。香の幻は、清盛の亡霊のように、後白河のお胸に、さまざまな追憶を当然、甦
らすからであった。で、いつかお用いになるのを嫌い、つい今日まで、筐底
におかれたままであったのである。
が、大原御幸を思
し召したたれた日から、後白河はひそかに、 「・・・・女院を訪う日の、みやげに」 と、お心にとめておられた。
建礼門院德子にとれば、それこそ懐かしい、在
りし日の父の香がすることであろう。父とともに在る心地を呼ぶ物ではないか。
── 御幸のおん土産
物 として、ほかにも種々
な品を御用意ではあったが、女院をなぐさめるには、これにまさる贈り物はあるまい。そう思われて、輿の内から、女院の喜ぶ顔を、瞼
にしておられる御 舅
君 の後白河法皇であった。
道は、いよいよ登りつめて、鞍馬の九十九
折 も、半ばまで来た。
そのまま、なお行けば、鞍馬山寺の山門である。が、御幸の人びとは、坂の途中から、北の細道へ、曲がって行く。
丈
なす夏草や、潅木 の茂みが、輿
だけを見せて、人の姿も覆い隠してしまう。
裏ケ嶽、二ノ瀬も過ぎる。
高地の爽涼
が、肌にせまって来た。霧の流れは、脚もとをめぐ っている。 ── 東は近々と、比叡の?気
に対 い、西には鞍馬山や貴船
山 や、丹波
の山波が、平行した視界のうちにないっていた。
「辺りは、静
市 野
とか申す山中のよし、お疲れでございましょうが、これよりは北へ、道も降りばかりだそうですから」
と、人びとは、おん輿の内を、仰いでいう。
汗をぬぐい、清水を汲み、供奉
の面々も、ひと息入れた。 ── そしてまた、薬王坂や江文の山里を、爪先下がりで下がってゆく。
大原は、降りつくした山峡だった。
「こんな所にも人が住むのか」
と、怪しまれるような草屋根が、所々に見え、四山から落ちあう水は、岩間を奔
り、道をせばめ、輿も行きなやむばかりである。 「寂光院は、どこぞ?」 と、幾たびとなく、山家
の者へ尋ね尋ねて、ようやく、それらしい一宇
の堂が、草生 と呼ぶ里の山蔭に望まれた。
「ああ、ここか。・・・・このような所にか」
輿を降り立たれた法王は、あやうげな石段を、幾歩かお登りになりつつ、辺りの様を、しげしげと、眺めておられた。
── これが、かつては、清涼殿や紫宸
の百官からも、天子の御母と仰ぎ侍
かれていた后 の住居か。あの清盛が、眼の内へ入れても痛くないほど可愛がっていたむすめの果てか。
・・・・茫
と、多感を禁じ得ないお佇
みを、そこの青苔 に久しゅうしておられた。
左大臣後德大寺実定やら、花山院大納言、そのほかは、はや、つた葛
や忍草 の垣
を前に、絶えて開けたこともないような朽ちたる小門をさしのぞいて、
「お人やある、お人やある」
と、おとずれていた。
けれど、一こう内の返辞もなく、ただ、深い山蔭の濃
みどり浅みどりの裡 から、岩肌を伝うて、奔々
と流れ下って来る不断の楽
が、耳を洗うだけであった。 |