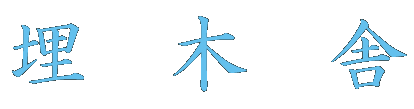「口惜しくは思うが・・・・、この薄金
の鎧 すら、今は身に重とうなった。何か、辺りの夕陽
の色も眼に痛い心地ぞや。・・・・兼平、死期は近づいたとみゆる」
「何を仰せられる。三軍の将たるお方は、たとえ、どんな苦境に立とうが、みずから、もう駄目だなどと、軽々、お命を見限るものではありませぬ。──
ここは兼平が防ぎますれば、殿には、先へお落ちなされませ」
「いや、あせっても、見も心も疲れ果てた。それに、いずこを見ても敵」
「やあ、ふがいないおん弱音。今日の戦
に、討ち死にした味方はまだわずかです。樋口を始め、太夫坊覚明なども、君やいずこと、御生死を尋ねているやも知れません。もし、殿が北陸にありと分からば、続々、お慕いして参りましょうず。そこまでの御忍苦もなしえぬ弱大将でもありますまい。木曾谷ごろの駒主が面魂
は、今日どこへ失うてしまわれましたか」
兼平は切々と、歯がみして言っていたが、
「── オオ、かなたからまた、敵が見ゆる。殿、殿。今のうちに」
と、急き立てた。
そして、大
長柄 の刃
の平で、義仲の馬の尻を強く撲
った。
馬は義仲を乗せたまま礫
のように飛んで行った。義仲は後ろ耳で聞いた。 ── そのあとに、わあっと揚がった喊声
の嵐を。
振り返ると、夕陽の下に、真っ黒な一隊の鉄騎が、兼平一人を押っ取り囲んだらしく見える。
── その兼平は、なるべく敵を他へ誘おうとするらしく、一角を突き破ると、さらに遠くへ遠くへと、敵勢を引き込んで行った。小さいその一点の人影は、冥途
の府の溶鉱炉 へ馳け込んで行くように、やがて、夕陽の果てへ淡
れてしまった。
義仲は、ただ一騎となった。一騎となればまた敵の眼も避けやすく、松原の木陰を縫いながら憩
い憩い北へ急いだ。
── と、意外にも、また前方の野に、武者の咆哮
が聞こえた。義仲は、道をかえようとしたが、ふと、自責に気も狂いそうになった。われも忘れて、 「こうなってまで、まだ戦っている味方は、そもたれか」 と、馬を向けた。
義仲の姿を知ると、そこの東国勢は、自分らの目を疑って叫びあった。
「あれよ、大将軍の装いは、まぎれもなき木曾殿ではないか」
「おう、義仲将軍ぞ」
「敵の総大将」
たちまち、旋風
は向きを変えて、義仲一人へ当たってきた。
甲斐
の一条次郎忠頼、土肥
実平 、武蔵
のなにがしと、続々、呼ばわりかかって来た。
死闘する義仲の耳には、それらの名のり名のりも、ただ肉声の怒涛
としか聞こえない。けれど彼はふと、一人の味方の姿を、重囲の中に、はっきりと見た。
それは、黒髪長き女武者であったから、入り乱れる他の人馬とはすぐ見分けがついた。わけて白銀
の天冠が、それを取り囲む坂東
武者のあいだに、生命
の明滅を告げるかのごとくキラキラしているのが彼の眼を射た。 |