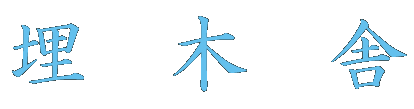「おう、巴だっ。巴よ」
義仲の一と声は、彼がこれまでの数々な戦場で叫んだどんな場合の声よりも悲痛であった。
けれどおそらく巴の耳には、届くまい。
間断ない馬蹄
のとどろきは、かなたの巴を追っかけ追いまわしつつ、また、義仲の姿をも捕捉
していた。相寄ることなど、不可抗力であった。
── が、義仲の死力は、一方を突き破っていた、馬も人もない狂奔の影がただ一文字に飛んでいる。そして、馬にも人にも、針鼠
のように矢が立った。
── やがて脚力の限界が来、馬の早さは、急に落ちていった。
── 淡
ら陽 の粟津
ケ原 を、その影は、よろめきよろめき、北を指していた。兜
の重さに、眉廂 もうつ向きがちに、人も肩で息をし、駒も脚も、おぼつかなげに、縒
れに縒れて行く。
── ふと、彼の頭のしんに、何一つ物音もせず、まるで氷界
のような空間が生じた。その痛いような耳の奥で、自分の名を呼ぶ巴の声だけがありあり聞こえた。聞こえるような気がしたのである。
「・・・・・・・」
義仲は、後ろを、振り向いた。
その眉、その眼もとは、すでに死相をおびている。仮面
に見る夜叉 のような、あの青さをたたえていた。
「と、巴
・・・・」
唇 は、呼ぼうとするが、もつれて、声も声にならない。
しかし、彼が生涯に呼んだあまたな女性の、どの名よりは、心から呼んだ真実の一と声ではあった。
するとそのとき、何かにつまずいて、彼の馬は泥田のなかへ落ち落ちこんだ。いや、それよりも、ひゅうっと飛んで来た矢が、喉笛
から内兜 を射抜いたことの方が早かったかもしれない。
いずれにせよ、がばと、大きな泥しぶきの音がした一瞬、さしもの木曾山の自然児、そしてわずかでも、覇
を都に占めた朝日 将軍
義仲 は、三十一を末期として、生命を終わっていた。
深田の泥へ、横顔の半分までも埋めたままの彼の死に顔は、白い夕星の下に、すぐ、比良
の雪のような冷たいものに化していた。
それは、なんの怨念
の影もなく、むしろ、課せられた宿業
を解かれて安らいだもののように見えた。
── たたたと、たちまち、ここへ馳けて来る騎影
があり、すぐ飛び降りた一人の武者は、義仲の首を持って、泥田の中からはいあがると、魔の踊りのように、その首をさしあげて、体じゅうから怒鳴った。
「木曾殿の御
首級 を、われ揚げたるぞ。──
相州三浦の住人、石田次郎為久、木曾将軍義仲殿のお首を取ったりっ。── 木曾殿をば、石田為久が討ちとったり」 |