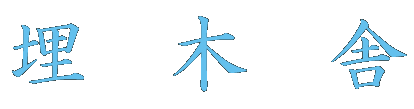醍醐
、山科 などの山づたいを、思い思いに逃げてきた味方の声で、今井兼平も、今はたふぁ一つしか残されていない自分の道を知った。その道を行き貫こうと決心した。
「頼重、残った手勢はどれほどか」
「なお、六、七十騎はおりましょうず」
郎党の二河次郎頼重は答えた。
兼平はその毘
沙門堂 から、ふともとの瀬田川、膳所
ノ浜 、粟津
ケ原 の遠くまでを見わたして、
「よしっ、行こう、一つになって、おれにつづけ」
丘を降りて、石山道へ打って出た。
彼の考えでは、もう、大将軍義仲も北国落ちへ急いだにちがいない。
「── ならば、生死を共に」 と肚
を決めたのだった。
けれども、それも容易なわざではない。東国勢三千余騎は、兼平が死力をふるって出たのを見、包囲に包囲を繰り返して、追いかぶさった。
兼平の部下は、次第に討ち減らされ、わずか十三騎になっていた。たったいま声のした二河次郎頼重も、いつのまにか、見えもしない。
「おう、いまのうちに、敵はおれどもを見失うて、あらぬ方へ馳けたぞ。ただ走れ」
偶然な空隙
を見出して、兼平らは、やや敵の重囲の外へ出た。
陽は傾いて、瀬田川の水も、湖
面 のさざ波も、朱金
のようにギラギラと眩
かった。そのため、山蔭の野や森は、かえって、はやい暮色をたたえ、身を晦ますには、絶好だった。
するとかなたから数騎の影が馳けて来た。相互で 「敵か?」
と立ちすくんだ、が、やがて先の者から、
「やあ、木曾輩
ではないか。おれは義仲ぞ。 ── 兼平はその中におらざるか」
と、叫ぶのが聞こえた。
「おう、わが殿か」
兼平と義仲は、馳け寄るなり手を取り合った。どっちも
「── 残念」 とのみただ一語、悲涙を見合うだけだった。
二人は竹馬
の友だし、義の兄弟でもある。苦楽を共に今日まで来て、木曾六万の兵もいずこ、無量な感に打たれずにいられない。
やがて、兼平が言った。
「無念は尽きませんが、かくお行き合いできたのも、まだまだ、天がわれらを捨て給わぬしるし、いざ、道を急ぎましょうず。時節を北陸の野に待って、今日の辱
を雪 がいでは──」
「もとより、おれもその心だぞ。だが、この小勢では」
「いや、諸所の山道より、落ち来る味方もありましょうず。しばし、木陰にてお憩
いあれ」
兼平は、山の中腹から、小旗を振らせた。
あちこちで寸断された味方だの、まだ宇治川から醍醐の峰づたいを彷徨
っている将士など、やがて百余人も集まった。
けれど、馬も持たない敗残兵である。敵中突破は、みすみす無理だ。とはいえ、止まるもまた、自滅のほかはない。いわゆる運命の賽を、みずから投げて出るしかない。
果たして、そこの山蔭を出るやいなや、つぎつぎに、強力な敵にぶるかった。
わけて、蒲冠者
範頼 の幕僚、稲毛三郎重成、榛谷
四郎 重朝
、一条忠頼などの手勢は、
「四天王の今井はあの中ぞ」
と、いいはやし、さらにまた、
「木曾の大将軍義仲も」
と見つけたので、おのおの、その大功を取るのは今ぞ、、この時ぞ、と奮
いあって、執拗 に、義仲と兼平たちへ食い下がった。
木曾武者の死にもの狂いも眼ざましかった。しかし、馳ければ遠矢野の的になり、迎えれば、眼に余る大軍の敵である。いつか義仲の前後には、幾騎の味方も見えなくなった。
このとき、多胡
次郎 家包
も戦死した。
「兼平、もういけない」
敵を馳け散らして、一息ついたとき、義仲は、心身ともに綿のような疲れを自分に知ったのであろう。── そのまま、馬のたて髪へうつ伏したいような息づかいをした。
「こは、お気弱な。いつものわが殿らしくもない」
わざと、兼平は、猛々
といった。だが、かえりみれば、西日の地上に細長い影法師を寄せおうていた者は、前後、自分と義仲のただ二人きりでしかない。 「── ああ」 と彼も内心、立ち暮れる思いを、どうしようもなかった。 |