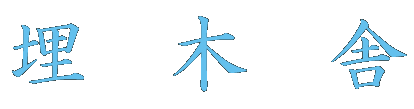「・・・・・・・・」
おそらくは、生まれ故郷の波音に耳を洗われ、七十余年の長い過去を、ふと、振り向いているのではあるまいか。
壮年のころ、長井ノ庄を領して、武蔵国に定住していた時代もあるが、彼の出身地は、越前南条郡の熊根村であり、遠い祖は、在原氏
だった。地方の文官だったのである。
幾代か前の先祖から、源家と結ばれ、源氏の粟
を食べてきたが、もともと、文雅の家の血を引いて きた彼なので、東国の粗野には耐えられぬ思いがあった。後、平家の右大将家に仕えて、老後を生きていたのも、人はなんともいえ、彼には希
う余生であった。凡々と、都の一隅
に、老い朽ちるこそが望みだった。
けれど、こう生きたいと希
うままに、生かさないのが世の中である。さきの富士川の戦いに当たって、恩義のある主の宗盛から、維盛について、軍監として征
くようにと、ねんごろな依嘱
をこうむった時、彼はすでに、老骨をもって恩に報
ゆる日と覚悟したのであった。
── だが、
彼には、自己の言葉を帷幕
に用いさせるほどな地位がない。門閥もない。
身分に過ぎたる宗盛の依嘱であった。
かえって、自分が軍監の大任をもってって征
ったために、富士川の陣は、よけい内輪がまずかったと考えられないこともない。
実盛は、すべてを、自分の落ち度としていた。あれ以後、ひとり心に詫
びて、
(老人というものの辛
さなのだ。責めを年下の者に負わすべきではない。しかも、お主
のおたのみを負うて陣に加わって征た以上、なべてのこと、一切の責めは、この老骨にある)
と、していた。
(それが、あの態
じゃ。富士川の大敗じゃった。未然に凶をおいさめしても、お若い公達
大将にきかれはせぬ。・・・・ぜひのう、陣地を捨てて、われ一人、先へ都へ立ち返って来た。そうしたら、お悟りあるやと思うたことが、人はわれを嘲
うた。いや嘲うたも無理はない。富士川の汚名は、平家の名とともに消えもすまい。みな、実盛が不つつかのせいよ。ふかく、わび申さにゃならぬ)
死所を富士川に得なかった彼は、こんどの、北陸発向こそ、
(死ぬときぞ)
と、ひそかに、誓って出たのである。
それとなく、宗盛にも、今生
のいとまを告げて立った。その際、彼は、
(北陸は、それがしの、うなれ故郷でおざる。ふるさとへは、錦
をかざれと、人も申しますれば、身に過ぎたるおねだりではありまするが、赤地
錦 の直垂
、萌黄 縅
の鎧 、くわ形のかぶと、鷹
の切斑 の矢など、大将の装
いを、おゆるし給わりませ。常の日、あだには用いませぬゆえ)
と、願い出た。
宗盛は許したし、それらの品々を、出陣の餞別
にと、彼に与えたのであった。
── かれが、いま、身にまとっている綺羅
な物具 は、しべてその折の品にちがいない。
「武門の生涯は身に染まぬ性
と悔いつつも、ついつい、腰のまがるまで、世をすごしてしもうたが、この賜物を着、故郷の土に死ぬるは、本意でないとは人にはいえまい。おおむね、本意なき死が人の世のならいであるのに」
こうつぶやいて、眼を、あたりへ配
り直したときである。
驟雨のように遠くの地が鳴った。 |