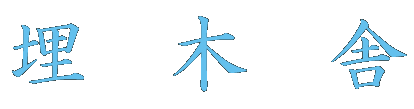とどろに、海鳴りが高い。果てなく見える白砂と白浪は、裏日本の夜の海だった。
一方は、そこに限界され、陸地も今江潟
、木場潟柴山潟などが寄り合っていて、平野の半ばは、湿地である。
平家勢の敗走路は、自然、狭められていた。四分五烈となって、浜を逃げ、野を逃げ、山蔭へさして走る大群もあった。蜘蛛の子を散るという言葉も当てはまらないほど、それは、おびただしい数の人馬なのである。
そして、維盛、通盛たちの主力部隊は、柴山潟と佐美ケ浜のあいだを、ひた走りに、逃げてくずれて行った。
砂丘が多い、松が多い。
根上がり松に足をとられて、人馬はやたらに転びあった。
平有国、範高
の二人は、
「あれよ、うしろの敵は、はや迫った。われらにて殿軍
つかまつらん。一門の方々には、ただつつがなく都へ帰り給うて、いつか今日の恥をそそぎ給え」
と、取って返し、木曾の追撃を、しばし必死にくいとめた。
だが、それも怒涛
へ向かうようなものでしかない。みるまに、死力の殿軍も、喚きにのまれ、敵の追撃力は、なお、拍車を加えてくる。
真下重氏、浮巣三郎なども、引っ返して敵に当たったまま、行方も知れず、高橋判官長綱も、踏み止まって、討ち死にをとげた。伊豆の伊東入道祐親の子、祐清も、このとき血戦の中に果てたのであった。
総じて、富士川以来、臆病風
は平家の旗には付きもののように世上にも言われたが、決して、そのような人ばかりではない。 ── 上総介忠清、その子太郎忠綱、洲浜
判官高能、尾張守貞安、摂津判官盛澄、越中太郎盛綱、射水
藤太俊貞など、きびすを回
しては、戦って討ち死にしてゆき、味方の主力を、危地から逃れさせるために、途上、眼をおおうばかりな屍を続々横たえていったのである。
なかでも、
「俣野
五郎 景久
」
と名のったある武者は、木曾の十三騎を斬って、自分も全身に創痍
をうけ、砂丘の松によりかかったまま自刃した。
あえない犠牲者のこうした支えで、維盛以下の主力は、からくも、虎口
を脱し、一部は大聖寺方面へ、一群は片山津から山代
、山中方面への山岳へ別れ去った。だが、逃げ遅れたか、なお、それに続いてゆく、ちりぢりな兵の影もある中で、寂然と、ただ一人で、砂丘の松の根に腰かけていた平家の一武将があった。
それは、かの斉藤別当実盛である。
先へ落ちて行った同陣の友に、わが愛馬も与えてしまい、多年、養ってきた家の子郎党も残さず、彼はまったくの身一つであった。
味方にもわざと離れ、敵の一団、二団の影さえ遣
り過ごして、何思うか、実盛は、ほっと息づきながら、この世の星と松風に、じっと老いの目を上げている。 |