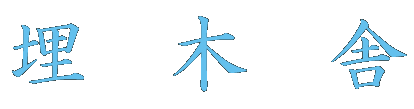おなじころ、かの経盛
が嫡子の、皇后 宮亮
経正
も、西下の人びとにおくれて、従者五、六騎を連れ、仁和寺の御室
ノ御所 へいそいでいた。
経正は、八歳の頃に、仁和寺へ入れられて、十三歳の元服まで、稚児
として、御室に仕えたことがある。
初歩の学業もここで受け、和歌、音楽、仏典などの躾
も、すべて任和寺で習 びを受けた。
── いわばここは彼の童心のふるさとであり、御室の宮は、師でもあり、里親
にも似たお人なのである。
「なに、経正とな」
番僧たちは、門を討ちたたく訪
れに驚いて、奥へ馳せ、坊官
の詰 の者に、
「夜来
、都は、未曾有 な異変の中にあるやにうかがわれまする。かかる中を、平家の客に門を開いてはいかがなもので」
と、すでに後日のたたりを恐れるような口吻
でさしずを仰いだ。
木曾兵はまだ洛中に見えないまでも、その圧力は、洛外諸寺院へ、もう、じかに伸
しかかって来ている。坊官も侍僧
たちも、
「うかとは、門を開けられまいぞ。たとえ、修理大夫殿 (経盛) の御嫡子であろうとも」
と、かたずをのんで、ためらった。
すると、御室
の侍者 、大納言の行慶
法印 が、この由を聞いて、そっと、宮の御意を伺った。
「むかし、稚児
としていた経正殿が、さいごのお暇にとて、御
門側 まで来ておりますが、どういたしましょうか」
すると、法親王は、
「経正が別れに来たか、時ならぬ時刻を思えば、なおさら、よくよくな思いと見ゆる。さしつかえない、内へ入れよ」
と、ゆるされた。
宮は、後白川の第二の皇子、守覚
法親王 である。稚児の頃から今日まで、宮の御愛情にもお変わりなかった。何かにつけ目をかけておいでだったのである。
侍者の行慶法印は、ふたたび、御前にもどって、
「思し召しを申し伝えましたるに、経正殿は、涙ぐんで喜びましたが、甲冑
をよろい、弓箭 を帯
して、あらぬ様なる装いに候えば、御前に罷
るも、憚 りなれと、なお、遠くに控えておりまする」
と、取り次いだ。
「あわれなる遠慮かな、ほかならぬ今の場合、日ごろの行儀
はいらぬ。その姿のまま、ただ、まかれと申せ」
行慶は、宮のお言葉を、経正につたえ、ほどなく、彼をうしろに連れて、御座
の間の前なる小坪 (小庭)
にひかえさせた。
その日、経正の装いは、紫
錦 のひたたれに、萌黄
匂 いの鎧を着、姿のよい太刀を帯
し、兜は脱いで背へ懸けていた。
重藤
の弓を横に、ぬかずいていると、出御
の声が高く揚がった。そして、
「経正か。よう見えた。これへ、これへ」
と、さし招くのは、まぎれもなく、なつかしいお方の声である。
「では、おゆるしを」
と、階 を上がって、経正は正面の大床
にあらためて座を賜り、さて ──
「行くては西海千里のかなた、またいつの日、お姿を拝しうるかどうかもわかりませぬ。すでに、みかどを始め奉り、一門落去
の途 に混みおいておりますが、つかの間、お別れに参
じました」
と、多年の恩育を謝した。
そして、供の侍、藤兵衛尉有教の手から、赤地錦のふくろに入れた一面の琵琶を受け取って、うやうやしく、御前にさし置いた。
宮には
「何か?」 とご不審な面持ちで、彼の姿と、その品とへ、等分に御眼をみはられた。 |