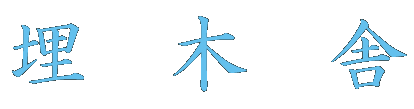経正は、つつしんで、
「これは先年、わたくしへ下
し賜った青山 の御琵琶でございます。思えば、身に過ぎたものですが、生来、琵琶を好み、手
解 きまでしていただいていた御縁をもって、わたくしが十七歳のとき、宇佐
の八幡 へ、勅使として下向いたしましたおり、おん手ずから賜ったのでございました」
「おお、そちが、宇佐の拝殿において、秘曲を弾き、供の宮人
や神職たちに、涙をさえ催させたといううわさは、ひところ、都の語り草であったるよ。その青山をば、何で今日、これへ持参したのか」
「家は捨て、都は去るも、なかなか、青山との名残は思いでございまする。さはいえ、さしもわが朝の重宝、玄象
、獅子 丸
とならんで、唐より海を渡って、いにしえは帝
の秘蔵にも封じられてあったと聞く、かほどの名器を・・・・いかにとはいえ、流亡の旅路へ、携えて参るには忍びませぬ。もし、荒ぶる戦いの間に砕くか、僻土
の塵 にでもしてしまっては、経正ごとき者の一命は果てこそあれ、御
国宝 の大きな失
いです。悔ゆるとも及びませぬ」
「・・・・うむ」 と、宮はうなずかれて、 「それゆえ、預けに持ってきたか」
「御意
のとおりです」
経正は、すずやかな眉をした。
「万に一つでも、ふしぎなる冥助
があって、もし今日の運命が開け、都へ立ち帰る日がありましたら、その時こそ、かさねて、経正に、青山を下
し賜りませ。・・・・が、おそらくは、このおん琵琶とわたくしとの、宿世
の縁も、今日限りかとぞんぞます。・・・・ただ、大唐
の朝 よりわが村上帝に伝えられ、後、師のおん手にも、朝夕御
鍾愛 あらせられたる名器を、たとえ幾年が間たりと、身に持って、転手
に手をかけたかと思えば、よき恋人と、宿世
を共にしたような歓
を忘れ得ません。・・・・過分な倖せであったよと思いまする。・・・・今は、末長く、御座のかたわらに置かせ給い、青山の音色
の蔭には、経正ありと、思し召しくださいませ。経正は死すとも、師の君のおつつがなきを、あの世からも、お守り申しておりましょうゆえ」
「・・・・・・・」
宮は、法衣の袖ぐちで、いつか、おん眼をぬぐうている。
経正も、あとは言葉もない
──。ただ、青山の一器を前に、冷ややかな大床に、身をひれ伏しているだけだった。
やがて、御室
の宮 は、
「・・・・料紙を」
と、侍者の行慶に命じ、行慶が供えた硯箱
の筆をとりあげて、 |
あかずして 別るる君が 名残をば
後のかたみに つつみてぞおく |
|
と、別離の一首を、経正に餞別
された。
「かたじけのう存じます」
押し頂いて、鎧下の肌着にそれを秘める彼の姿を見て、宮は、
「経正にも」
と、侍者の手から硯を与え、彼の返歌を求められた。
経正は、料紙をいただいて、それへ、 |
くれ竹の 筧
の水は 替 れども
なほ住みあかぬ 宮の内かな |
|
と書いて、お答えした。
「やさしさよ」
と、幾度もお口のうちで誦
みながら、法親王の宮は、なお涙をあらたにした。しかし、とこうして、空は白みかけている。名残は果てしない。経正は、さらに、まじまじとお顔をながめ、さいごの一礼をして、床
を降りた。
ひそかに、前後の様子を、垣間
見 ていた仁和寺の童形
(稚児) や坊官や侍僧たちは、
「あわれ、ふたたび帰らぬ人の立つ」
と、門前まで、見送って来て、別れを惜しんだり、慰めたり、励ましたり、いずれも、袖を濡らさぬ者はいなかった。
中でも、法印
行慶 は、葉室
大納言 の子で、経正が稚児の頃から、仲のよかった友だちでもあったから、経正が、
「もうよい、いくら送ってもらっても、名残は尽きないから」 といっても、 「もう少し先まで、いやそこまで」 と、いつか桂川のほとりまで一緒に来てしまった。
行慶も、そこで、 |
あはれなり 老
木 若
木 も 山ざくら
おくれ先だち 花は残らじ |
|
と、別離を詠
んで、友に示した。
経正の返歌には、 |
旅ごろも 夜な夜な袖を かた敷きて
思へば我は 遠く行きなむ |
|
と、あった。
「行慶どの、さらばぞ」
自分を鞭
打つように、そう言い切ると、経正はもう後を見ずに駒を飛ばしていた。
やがて、約束の所に待ち合わせていた彼の手勢が、彼の来る姿を見るや、旗を振って、彼の前後に、むらがり寄って来た。そして、川霧の果て、淀のあたりに、主上の御輿
の頂が、朝の陽 に、きらめくのを見、急ぎに急いで、やっと、追いつきまいらせた。 |
| 『新・平家物語(九)』 著:吉川英治 発行所:株式会社講談社 ヨ
リ |