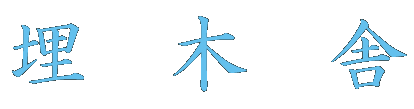俊成
は、歌人である。
左京
大夫 とか皇太后宮大夫
などを歴任しが、和歌の道よりほかに、栄誉もかえりみない人だった。
息子の定家
と一緒に、早くからこの京極の家に、半
隠者 的
な生活を愛し、請 われれば、たれjかれなく、詠草なども見てやっている。──
そして、若い頃から六十代の今日まで、変わりなく文通している道の友には、かの西行法師などもあった。
その西行も、都へ来れば、かならず俊成の門を訪ねた。
── 近ごろは、高野
の蓮華院にいるらしく、つい数日前も、高野から便りがあったばかりである。
西行の便りには、
(── このごろ、人からうけたまわるに、院の御命をこうむって、いよいよ、千載集
の御 編纂
にかかられたとのこと、歌道のため、喜びにたえません。けれど、朝に夕べが計られず、夕に明日も知れぬような世間の中では、撰集のお仕事も、おたいていではありますまいそれだけにお仕事の意義も、後の世にかけてまで大きなものともいえますが、何しろ御重任です。切におからだをおいといくださいますように)
などとあって、いつものような自詠の歌二、三首が、添えてあった。
後白河法皇が、
「千載和歌集」 の撰 を命じられたのは、ことしの二月ごろであり、完成には、この先、幾年かかることやらわからない。
当代の歌人、非歌人をとわず、およそ歌心のある者の秀歌を、つぶ選
りに選 び集めて、千載に遺そうという思し召しによるのである。老齢な俊成としては、もちろん、これを自己の歌人生活の、最後の仕事としていたろうし、また、歌ごころを持つ世の人びとは、たとえ一首でも、その中に選ばれる誉れを得たいと希
ったにちがいない。
歌には、興亡もなく、栄枯もない。いかなる勲爵も物質も、うたかたに過ぎなかった。ここ数十年のちまたはそれの実証であった。
人の白骨化さえ待たないほどそれは頼みにならないものである。しかし、一首の秀歌は、千載集に遺ってゆく。心の匂
いを伝えてゆこう。── これこそ輪廻
の外に立つ不朽の塔だ。 ── そうしたあこがれに違いない。人の生命
も植物の本能に似て、何かの花粉を、その散り際には、自然、地上へこぼしてゆきたがるものだった。
「・・・まこと、忠度
殿 でおわしたの」
俊成は、縁にすわって、庭を見た。
すすめられたが、忠度は、
「先を急ぐ供奉 の途中、かつは、甲冑
の装いなれば」 と上がらなかった。
ただ、露深い庭草の中に、ひざまずいて、
「心ならずも、常には、お門辺
へも、不沙汰ばかりしておりまして」
と、謙虚にわびた。
「なんの、世上、ただならぬ風浪、よそながら、お察しは申しておる。わけて、和
殿 は、亡き太政入道殿が、おん義弟
。いや、おたいていではあるまい」
「されば、世間、しずかなる日は、つねづね、拙
き歌ぐさを携 えて、何かと、お教えをも賜りましたが、ここ両三箇年があいだは、国々の乱れに、都におる日も少なく、手は弓に奪われ、身は鎧にいましめられ、お便りすら、つい怠っておりました」
「して、にわかなお訪ねは」
「ついに、大事は一門のうえに及び、今晩、主上のもすでに帝都をのがれさせ給い、遠く西国へ落ちゆくことになりましたゆえ」
「や、や、では主上にも」
「思いまするに、われら平家の輩
が、再び都に帰って、昔日の栄えに会う日は、もうありませぬ。運命今日に尽きたるものと存じまする。それにつけ、はかなき夢を追うのではございませぬが、その後、戦の暇や、草を枕の野辺にて、おりおりに、詠み出た歌を書きとめておいたのが、いつか、この一帖に百首あまりとなっております・・・・」
「・・・・・・・・」 |