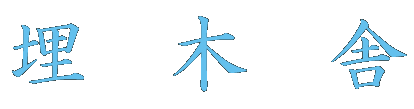「おそらくは、師の御丹精がいもなく、いつまで、花らしき花も結ばぬ拙
い歌ばかりでしょうが、自身では、常に明日の生命
の知れぬがままの、偽りなき、虚心をもって、詠
み出たものに違いありませぬ。・・・・が今は、反古
さえ心の荷、川に捨んか、火に焼かんかと、まどろいながらも、いやせめて、いちどでも、師のおん目を通していただけたらと。欲をいだいて、これへ持ち参ったのでございました」
「・・・・・・・・」
「うわさには、千載集の御撰
にかからせ給うとうけたまわっておりますが、武骨者の幼稚な歌などを、それにと望むのではございませぬ。かえって、昼夜なきおいしそみのおり、心無き儀と、恐れ入るのでございますが、平家のともがら、一門二十年余の都を去るにのぞんで、一首の歌だに、都にとどめた者もない。といわれるのも口惜しゅうてのことでございまする。・・・・あわれ、御門下の端に、かかる男もいけるよと、徒然
のお暇になと、お目 通
し給われば、あとは、庭の落葉とともにお焼き捨て給わろうとも、お恨みには存じませぬ。それをもって本望といたしまする」
「・・・・・・・・」
俊成は、まじろきもせず、庭面の人の影を見ていた、感動を感動のままに措
いて、言葉にすることを忘れている。
そのあいだに、忠度
は、鎧 の脇立
の紐を解き、ふところから一綴
の帖 をとり出して、身をすすめた。そして、
「「お恥ずかしゅう存じますが」
と、縁のはしに置いて、またあとへ退がった。
俊成は手に取り上げた歌の帖を、しばらく見ていたが、やがて、心から心へ、しかと約するように、静かに言った。
「日ごろの心忙しさにさえ、なかなか、人は取
紛 れるもの、まして御一門都を落去、あと先も、ただならぬさいに、ようこそ、お訪ねくだされた。
── この詠草 とてまた、血ぐさい兵馬にあいだに、やさしきお心がけを留めておかれたもの、いわば歌の一首一首が生命
のお形見であろう。歌 詠
まんがための作り歌とは事ちがう。ゆめ、疎略
にはいたしますまい。 ── 忠度どの、おかたみは預かった。心おきのう、西国へお立ちあれや」
「ありがとう存じまする」
露の中に、その人影は、ひれ伏して、
「いずれは武門の末路、屍を野にさらし、はかなき名を、西海に流すことでしょうが、これで、思いおくこともありません。・・・・さらば、おいとま申して」
と、庭戸を辞して、もとの槐
の木下に立った。
かぶとの緒
をしめ、駒にまたがり、数歩去ったが、去りがてに、その影は、もいちど、槐
の門を振り向いていた。そして、和
漢 朗詠
集 の中の、
前
途 程
遠 し
思ひを雁山
の夕べの雲に馳 す
という一詩句を口誦
さみながら、まだ暗い朝霧の中へ馳せ去った。
俊成は子の定家
と共に、門まで出て、その姿を見送っていたが、父子ともに、涙を目にため、やがて黙々と門をとざした。
忠度が遺した自集の帖には、秀
れた歌が少なくなかった。── それから年月
も流れて、もう名ある平家
人 のたれひとり世に存在しないころになっても、俊成は、おりあるごとに、忠度の歌がたみを取り出しては、そのときのことを、人にも語った。
また、彼の撰
になる “千載和歌集” もやがて大成されたが、あまたな歌人
才媛 の代表的な名歌のうちに、
「故郷の花」 と題して、
さざ波や
志賀の都は荒れにしを
むかしながらの
山ざくらかな
の一首が載
せられてあった。これは、 「秀歌のなかの秀歌である」 と、人びとの愛誦
にのぼったが、作者の名は、 「詠
み人 知らず」 になっていて、久しく、そのたれなるやもわからなかった。
忠度が遺した百余首
の中の一作だったのは言うまでもない。しかし、平家没落と共に、みな、“勅勘
” の科人 となり終わったので、世をはばかって、俊成がわざとその名を伏せておいたのである。
しかし、さらに時世も鎌倉に移って、俊成の子、藤原定家が、
「勅撰集」 を編 んだときには、公然、薩摩守忠度、と名もあらわに再録された。
|