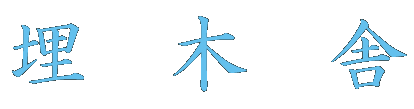ここにまた、薩摩守
忠度 は、主上
の御 輿
に従って、いちど六波羅泉殿
を立ったのであるが、途中何を思ったのか、供奉
の列を脱 け、侍五騎に、童
武者 一人、自分ともわずか七騎ほどで、元の道へ取って返した。
そして、五条京極
の近くまで来ると、従者に向かい、
「人目だたぬよう、しばしこの辺りに待て」
と、とどめておき、自分だけ、一つの小路を曲がって行った。
いずこの邸宅も真っ暗である。燈影はおろか人も気配もない。
やがて彼は、大きな槐
の下で、そっと、鞍 からとび下りた。手綱を、その幹へまわして結いつけながら
── 「ああこの門の槐の木、お前とももう別れだなあ」 と、言いたげに仰向いた。
年ごとの初夏ごろには、あの小さい蝶形
の内気な花が、門にも地にも、いっぱいのこぼれ、客の足痕
が、淡雪 を踏んだようにあとに残る。
そのころの静かな世間や、心の愉しめた日のことどもが、ふと忠度
の胸をよぎった。彼が、ひそかに恋していた意中の女性も、この門辺
に牛車を止め、おなじ槐の花の淡雪に足跡を印していた一人であったのではあるまいか。 ── でなかれば余りにも、ものいわぬ槐への多感な彼の佇
みであった。
「昨日 今日の騒がしさに、もしや、難を避けて・・・・?」
彼は、門のそばへ歩み寄った。
そして、はや、ここも空家ではないのかと、内をさしのぞいてみた。
よその公卿門とちがって、黒木の柱に柴
をあつく葺 き、竹を編
んだ袖垣 に葛
かあけびの葉が絡 み茂っている。
── 忠度は思い切ったふうで、そこの扉を、がたがた揺すぶったり、たたいてみたりして、
「時ならぬ今ごろ、心なき訪れなれど、俊成
卿 のおん内へもの申す。
──御 弟子
か召次 の方などあらば、開けて給われい。ここへお顔なとかし給え」
と、何度も言った。
答えはない。人の来るらしい物音もしない。庭の内は、月の色と露と虫だけの静寂
であった。
「やよ、開け給え、師の君へ、お別れを告げばやと、お門辺まで立ち寄ったるなれ。── 決して、怪しい者ではない」
すると、虫のすだきを、しばらく措
いて、やっと、邸内のどこかで、
「誰
ぞ?」
と、問う声がした。
さては、人がいたかと、
「さん候う。忠度
」
と、すかさず答えた。
それまでの静けさとは打って変わって、急に、物
怯 えする屋の内の騒
めきが外までもれてきた。 「押し込みよ」 「いや、落人
の逃げ戻りよ」 「どうしたものか」 などという切れ切れな言葉も聞こえる。
忠度は、一段と声を高めて、
「これは、今生
のおいとまを兼ね、師の三位
殿 (藤原俊成)
に、ささやかなるお願いの候うて、供奉
の途中より、しばし、返し参ったる西八条殿 (清盛) の義弟
、薩摩守 忠度
にちがいありません。世上の物騒、無理ならねど、なお、恐ろしゅう思し召すなら、この垣際
まで、お立ち出でください」
「・・・・」
「たとえ、門の戸は、開けずともよし、どなたなりとも、ここまで来て給わるまいか。お取次ぎだけでもしてくださるまいか」
忠度は、しきりにたたく。──
余りに供奉の列に遅れてはと、心も急ぐので切々
と言った。
さきから、門の内に息をのんでいた藤原俊成は、初めて、縁
の端へ姿を見せて、
「おう、覚えのない声ではない。かの人なれば、歌の門人、久しく、歌も寄せず、姿も身なんだが、時も時、何事の訪れやらん。・・・・ともあれ、開けて、お入れ申せ」
と、召使へいいつけた。
|