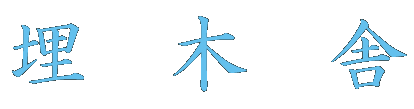年は暮れて、仁安三年の初春の事である。
西八条から使いが来て、
「仏
御前 が、つれづれ気
に見ゆる。会いもしたいし、遊びに来よ」
と、清盛からの、伝言であった。
妓王は、腹が立つやら、口惜しさに、
「いやです、お伺いは、かえって、お目ざわりでしょう。それに風邪
ぎみですから・・・・」
と、二度までの招きを断った。
彼女の母は、あとの咎
めも惧 れたし、また、西八条殿が、思いなおされたのかもしれないと、諭
して、気のすすまない妓王に、強
って、化粧をすすめた。
「・・・・でも、一人ではいやです。いまさら西八条に伺う面
もありません」
「妹の妓女
を連れておいで、ねえ、気を取り直しておくれ、後生
だから」
母にそう泣かれると、妓王はもう何も言えない子であった。
家へ帰ってみると、父の良全は、まるで人が違っていた。女房泣かせの極道者
に成り果てている。
妓王が家に戻ってからは、自暴
がつのって、酒乱にはなるし、外で喧嘩はしてくるし、賭博仲間の借財に、首もまわらない有様である。── どこまで悲運な母なのであろう。自分は薄命でも、母は倖せにいるであろうと、西八条にいるうちも、それだけは、ひとり慰められもしていたのに、と妓王はやるせない虚無
さにとらわれた。
「・・・・では、お母様のためにと思って、一度だけは、お伺いします。その代わりに、妓女のほかに、妹の友達も二、三人誘ってください」
彼女は心を決めて、招きの日に、西八条へ出向いた、妹の妓女と、友達の白拍子たちと、四人が一つ車に乗って行った。辱
と肩身の狭さに、妓王は、棘
の門を通るような気がした。
やがて、大殿
へ導かれたものの、かって彼女が召された辺りまでは、通されもしなかった。はるか遠い下床
に、座敷をさだめられて 「そこに、控えていよ」 と、家臣たちにさえ、冷ややかに扱われた。
仏御前は、清盛を責めた。
「せっかく、使者をやって、お招きしておきながら、座敷を下げて、あのいうに区別なさるのは、まるで恥をかかせにお呼びになったようなものです。妓王さまを、あのようにお扱いになるなら、わたくしもこの席にはいられません」
清盛は笑い出した。
「そなたは、まるで駄々っ子だな。妓王に会いたいというから呼んでやったのではないか、どうすればよいのか」
「わたくしと同じようにして下さいませ」
「では近々と、招くがよい」
仏の感傷にも、妓王の感傷にも、清盛はまるで無関心な様子だった。おかしいといえば、木の葉の舞うにも笑いこけ、かなしいといえば、花の散るにもすぐ涙をこぼす年ごろの女たちを、清盛は、しいて理解してみようなどとは、考えてみたこともない。
「妓王と、そこな白拍子ども、仏御前が、ああ申す。近くへまで、寄ったがよい。──
そして仏のつれづれを、慰めてやれい。今様
を歌うなと、舞 を舞うなとして、いつも浮かぬ仏御前を皆して慰めよ」
正殿の清盛の座
、脇 の座
、細殿 にも、この日、公卿の客やら、一門の平家人
たちが、居流れていた。廊には、諸大夫や侍たちの顔まで見える。こういう中で、清盛は言ったのだ。 「仏を慰めよ」 と、そして 「客のために見せよ」 とは言っていない。
妓王は、床に手をつかえて、
「──
畏 まって候う」
と、小声で答えた。
面を下げたはずみに、こられていた涙が不覚にこぼれた。自分に虚栄はないと、つねに虚栄を蔑
んでいたくせに、今の身のみじめさが、蝕
い入るように、胸をかんだ。嫉妬
に沸 られる心の揺れを、どうしようもなくて、しばしそのまま姿を持ち支えていた。
「いかがいたしたぞ、妓王」
たれかの声に、耳を打たれた。妓王は、はっとわれに返って、はふり落つる涙もぬぐわずに、今様
を歌った。 |