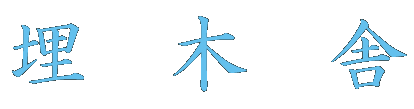その年の春、嵯峨
の奥、往生院
のそばに、草の庵 を結んで、住みはじめた母子
の尼がある。
妓王と、その母とであった。
幾日もたたないうちに、また一人の初々
しい若尼が加わった。妓王の妹の妓女である。
「そなたまでは・・・・」
と、母も姉も、彼女の黒髪を惜しんだが、極道
の父良全は、朽縄 といっしょに、そのころ、都から姿を消して、生死も分からなくなっていたし
── それは姉の悲運を見たり、富貴の悪戯
を見たり、世間にも、遊びの世界にも、いとわしくなって、
「わたしも、おかあ様のそばにいて、お姉さまと一つに、女の一生を、清々
と通してゆきたい」
と、せがむままに、やがて彼女も一つの庵に念仏して、侘
しくも、水入らずの草庵暮らしをともにすることになったのである。
平安朝の遠い世ごろから、女たちは、女の自由を、貞操の限界だけでは、かなり放縦にされてきたが、結局、かの女たちは、貞操だけの自由に今は疲れ果てていた。──
もっと広い自由に何か欠けていたからである。人間としての自由はない。彼女たちは、白拍子でなくても、つねに男のもてあそびものであった。
惜し気もなく、黒髪を捨てた女性たちの、なんと、この時代には、多かったことか。
それはみな、彼女たちの、弱い苦悶
の魂の、もがきでないものはない。
── 栄華や富貴は夢の夢よ。
── 世は浮世、まことの世は彼岸こそ。
── 後世の願いこそ大事なれ。
──
人の身は受け難く、仏縁には会い難し。
といったような考え方が、男といわず女といわず、いつも生活のかたわらでささやいていた世代でもある。ややもすれば、人間の困憊
は、
「仏陀のおひざもとへ・・・・」 を、願いとした。
それは、生命
を捨てない自殺、死まで行かないある形の死 ── ともいえる生死の中間をとった特殊な生存の仕方であった。
妓王の剃髪
も、その母の出家も、そうした世風の外の出来事ではない。妓女の純情は、まだ男性にさえ、未開花の乙女だけに、なおさら可憐
しいものだった。ただ時代の信じるものを信じて、墨染めを着たまでのことであろう。
ところが、またその後にも、もう一人の美しい尼が、この庵へ来て、妓王母子と、ひとつに暮らした。
仏御前である。
やがて、仏御前も、西八条の栄花の門をのがれ出していた。そして、ある夜、奥嵯峨の柴
の戸をほとほと叩 いた。妓王が出てみると、もう墨染の法衣姿
となっていた仏御前であった。
「まあ、どうして?」
と、手をとり合って、内へ入れ、夜もすがら、炉辺
に思いを語りあった。以来、四人一所
に、一つの蓮 の誓いをちぎり、朝夕念仏を唱えて、往生の素懐
── 仏教的な生活を、長く、つつがなくここに送ったというのである。
いずれも、あわれというほかはない。
もし鉦
の音のもれる垣間
見 に、さしも聞こえのあった都の名妓たちの、寒々
と、黒髪を剃 りこぼちている姿を見かけたなら、たれでも、不愍
を禁じ得なかったであろう。
── されば、後白河法皇の長講堂の過去帳にまで、妓王、妓女、その母、仏御前などの四人の名が書き入れられたほどだが、果たして、後白河のお心であったかどうか分からない。
もしまた、清盛が、妓王と仏御前の出家を聞いたら、何と言ったであろう。おそらくは、大いに笑ったにちがいない。そして、あたりの侍者へ、例の調子でこうも言ったことであろうか。
「わからぬよ、どうもおれには、性来、おれは女の心を解さぬ男に出来ているのだろうか。・・・・それにしても、どうして若い女どもが、やたらに髪を切りたがるのであろう。こんな流行
りは、止めさせねばいかん。男の入道
とは、わけがちがう。姿ならままよ。可惜
なものだ。 ── 清盛の室の花であろうとなかろうと止めさせねばいかん。浮世のながめが淋
しくなる・・・・」 |