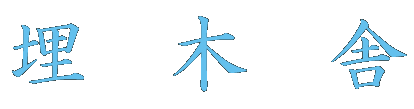仏は、西八条に、留めおかれた。
そこへ行った日が、嫁いだ日みたいに、ふたたび、もとの町に、帰らなかった。
妓亭には、使者が来た。妓亭の主は、祝宴を開くやら何やら有頂天である。うわさは、ぱっと、ひろまって、
「また、相国 のお浮気よ」
と、都の秋の辻々
に、そのうわさを聞かない日はない。
けれど、相国清盛の恋は、町の想像のようなものではなかった。
仏は、妓王の情けを忘れてはいない。妓王に義理を立てて、なんとしても、清盛の意に従わないのだ。べつに深い欲望とてない十六の乙女である。自分に優しい人を悲しませて、その人の寵
を奪うなど 「身にも恥ずかしく、浅ましゅうて」 と、顔を振るばかりであった。そして幾日も、
「・・・・帰してください」
と、訴え続けた。
「妓王がいるからそう考えるのだ。あれにはもう女の倖せをつくしてやった。行く末、どうなと安楽に暮らして行けよう。妓王には、暇
をやれ」
清盛は、侍者
の一人に、いいふくめた。
妓王にとっては、それは願ってもないことでありながら、こう言い渡されると、やはり綿々
と、尽きない恨みやら悲しさにかき乱されて、ひと夜中、衾
を被 いて泣きぬれた。
ほんとの恋は、忠度
に寄せていたのである。おととし、いそいそと、六波羅へ使いに立ったのも、その忠度に、よそながらでも会えることの嬉しさからでもあった。
── が、運命の悪戯
は、その夜、清盛の室へ彼女を追い入れてしまい、恋は、胸の奥所
に、生き埋めとなってしまった。以来、その忠度の姿を、一つ館
のうちに見かけることもあったが ── ふと、相見るたびに、恥ずかしさ、うしろめたさ、口惜しさ、たれにもいえぬ思いであった。
それなのに今、去れと暇を出されれば、妓王はそれにも、身を揉
むばかりの悲嘆にとらわれた。なぜであろうか。彼女にすら分からない苦しみだった。胸に、胸のうちだけの恋を秘め、そして、女の体と言うものは、まったく他の男へ託しきってしまった者にだけ生じるふしぎな内面の鬩
ぎであった。心は一つしかないはずのものでありながら、二つの心が自分の中に住んでいたことを思い知る苦悶
の怪しさは、産婦の陣痛のように、女性だけが享
けて生まれたもののようである。その不公平な生理や心理を、どうしようもなくただ泣きもがいて来たその時代の女性たちは、わらとわが身を 「罪深い女の身・・・・」
といい、 「・・・・女は魔性のもの」 と、考えたりして、宿命にも泣くのであった。
しかし妓王は、夜が明けると、いつものように、きれいに朝化粧をすましていた。
そんなにまで、夜を泣き明かしたとは、たれにもさとられないほどにである。
女童
たちに、室内を掃き清めさせ、好きな香を焚き込めなどした。その様子は、あくまで、理知で冷静なひとに見える。 ── 明日香
と呼ばれていた童女のころから、どこかにそういう風な彼女ではあった。彼女の恋が、第一の恋も第二の恋も山吹の花のように、実を結ばずにしまったのも、そういう知性に片寄っている性格が、知らず知らずに、きょうの運命を、自分で作っていたのかもしれない。
やがて、妓王はそっと、車にかくれて、西八条に門を出て行った。
去るにも、秋草の露をこぼさないそよ風のように、いかにも物静かであったので、人々は、よほど時経ってから、彼女がもう居ないことを、うつろな彼女の部屋に、初めて知ったほどであった。
そしてまた、人々の眼は、そこの障子
(からかみ) に、妓王が形見ぞと書き遺して行ったらしい一首の和歌に、いつまでも、ながめ入っていた。 |