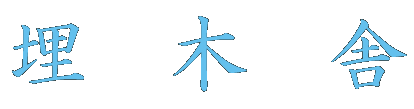目
ぶかに笠かさ を被かむ
らせ給い、旅僧めいたお身なりで、後白河はさっきから山門のやみふところに佇たたず
んでおられた。
資時の家の朗従数名がおそばにいた。
ふもとまでは、馬だったが、山道は、この者どもがお手を扶たす
けたり腰を押し参らせて来たのである。
それにしても、どたん場へ来て、宗盛に背負い投げを食わせ給うた手際といい、この夜の大胆細心だいたんさいしん
な御行動ぶりといい、貴人に似げない放れ業だ。武将もなし得ない奇略である。
が、御自身は、そんな危ない道を突破したともしていないような御容子で、
「おそいのう。・・・・資時は何しておるのか。誰た
ぞ、見てまいれ」
と、一人をして、そっと、東光坊の内をうかがわせにやり、笠に手をかけて、ふと、京の空を振り返られた。
大きなお顔だ。お体つきもだが、眼、唇くちびる
、耳、みな人なみ以上大まかで線が太い。魁偉かいい
な相そう といえばいえる。
亡き清盛より九ツ下であったから、お年は五十七のがずだが、どこにも老人臭しゅう
がない。やや赤味をもつ柔軟な皮膚も、なお五欲五情への旺さか
んな光沢こうたく のようである。
「お待たせ仕りました。律師りっし
覚日に会い、諸事、打ち合わせましたゆえ、ご懸念なく」
ほどなく、右馬頭うまのかみ
資時すけとき は、東光坊から戻って来て、後白河の前にぬかずいた。そして、黙々たる人影に迎えられて、後白河御自身も、やがて東光坊の内へそのお姿を隠された。
東光坊では、とりあえず、法皇がお憩いこ
いの間に、あたたかな供御くご
(食事) などさしあげ。資時と覚日らは、別室に額を集めて、
「どこにお匿かく
まい申し上げたがよいか。そして、もっとも御安泰ごあんたい
であろうか」
を、すぐ協議した。
覚日たち、鞍馬側くらまがわ
の意見としては、
「ここは安全とは申されぬ。もし平家勢が、お迎えに来きた
れりと称して押し襲よ せたら、拒みきれるほどな武力もないし、かつは、洛内にも余り近すぎる」
と、いうことであった。
そして、お疲れでも、もうひと足のばして、叡山まで行けば、御安心であろうにと、みな言った。
資時にも異議はない。
しかし、叡山は昨今、木曾義仲の本陣地となっている。
その義仲のふところへ、法皇が逃げ込まれたような格好になるのは、どんなものであろう。政治的にも、面白くないのではあるまいか。
すでに、そのお考えもあったからこそ、そこは避けて、鞍馬へ落ちて来られたものであろうことは、たれにも、察しるに難かた
くない。
資時は、叡慮えいりょ
を推お しはかって、まず十中八、九は、お聞き入れあるまいと思った。ところが、後白河は、一同の意見を聞かれると、
「では、叡山へ参ろう」
と、事もなげな御同意である。
しかも、今しがた粥かゆ
の箸はし を措お
かれたばかりなのに、すぐまた足に草鞋わらじ
のお身支度だった。御精力よと、驚かぬ者はない。
「通い馴れた裏山道です。叡山までは、われらが御守護もうしましょう」
と、覚日以下、鞍馬法師数十人が、松明たいまつ
をかざし、あと先に立って、そこを出た。
そして、それからの途中であった。
いつもの夜明けなら、東天から紅あか
らむはずなのに、西南の空が真っ赤に見え出した。
人びとは口をそろえて、
「洛中は大火と見ゆる。平家が放った火か、源氏の放った火か」
と、恐れ合った。
ちょうど、その時刻ごろ、六波羅や西八条では、平家自身の手で家々の焼き払いが行われていたのである。
道の熊笹くまざさ
も、法皇のお顔の隈くま も、赤く染まって見えるほど、そのはるかな火は、次第に大きくなっていた。
笹の峰、薬王坂やくおうざか
など、数里の山坂や谷を越えて、やがて二十六日の朝、叡山の横川解脱谷げだつだに
へ着いた。
ひとまず、法皇は、寂場坊じゃくじょうぼう
に入って、おやすみになり、覚日から三塔の大衆へ、事の由を告げ知らせた。── 山門の驚愕きょうがく
はいうまでもない。即刻、御輿みこし
を用意してお迎えの武士や大衆がやって来た。
「ここは不便、東塔とうとう
へこそ」
御輿に乗られて、その日、山から山へ移られた。守護の多くは、山門大衆であったが、いかつげな木曾武士もたくさん交じっていた。
聞こゆる木曾武士なるものを、後白河がおん眼に見られた最初である。
東塔の南谷円融坊えんゆうぼう
は、即日、法皇御所となった。
ひとたび、御座ぎょざ
をすえられると、寺門は、たちどころに、武者の甲冑かっちゅう
と、山法師の大薙刀おおなぎなた
に守られて、もう、胡散うさん
な者など寄りつきもしえない不思議な威容になった。 |