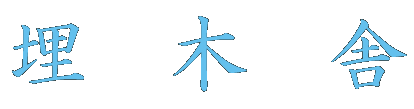ここの鞍馬山
鞍馬寺は、およそ何一つ変わっていない。むかし遮那王しゃなおう
牛若うしわか がいたころも今も、十年一日の如しである。山門は山門のまま天狗杉てんぐすぎ
は天狗杉のまま、不断ふだん の山風は飽きもせず、おなじ音階を繰り返している。
その夜も
── というのは平家都落ちの当夜のこと、時刻でいえば、かの宗盛以下が一門の古巣に火をかけて都を出る直前、七月二十五日の真夜中のころだった。
墨のよぷな山風に吹かれながら、一人の公卿が、鞍馬七坊の一院、東光坊の小門を打ちたたいて、
「深夜、不時の訪おとず
れながら、火急、阿闍梨あじゃり
にお目にかかりたい」
と、内へ申し入れていた。
番僧たちが起き出してきて、いぶかり顔に 「どなたで在わ
せられるか」 と訊ねたが、 「お目にかかったうえならでは」 とのみ名も告げない。ただ、その人のいやしからぬ風采ふうさい
と、何か非常な立場にあるらしい様子が、察しられるだけである。
ともあれ、番僧は奥院へ取次いだ。おりふし阿闍梨蓮忍は老病で半年も前から臥床がしょう
中ちゅう である。律師りっし
覚日かくじつ が、代って会った。
二人きりで一室に対座した。そして燭しょく
を間に、顔を見合わせるとすぐ覚日は眼に驚きをあらわした。
「や、資賢卿すけたかきょう
の御子息、右馬うま 殿どの
ではおわさぬか」
「されば、院の右馬頭うまのかみ
資時すけとき です。父の按察使あぜち
大納言だいなごん 資賢すけかた
を御存知か」
「近ごろは打ち絶えておるが、むかしはよく俊成卿しゅんぜいきょう
の月並つきなみ の歌会うたかい
などで」
「では、覚日御坊かくにちごぼう
と申さるるのは」
「野僧やそう
でおざる。阿闍梨あじゃり は、久しい間、老病で寝ております。このような山中へ、しかも深夜、いかなる御用のあって」
「じつは、院のお旨むね
にまかせ、密ひそ かにこれまで、おん供いたして参ったのですが」
「院と仰せあるのは」
「申すまでもなく、後白河の法皇きみ
です」
「えっ?」 覚日は自分の声に驚いた。仰天したのである。相手の顔を穴のあくほど見すえたまま ── 「まさか、お戯たわむ
れとも思わぬが、さりとて、院おんみずから、夜半の山路をこれへお登りとは信じられぬ。あすにても御参詣ごさんけい
あらんとのお先触れにでも」
「いやいや、御自身すでに、渡らせておられまする」
「はて、供奉ぐぶ
の諸卿もおつれなく?」
「資時一人いちにん
が、お供申し上げて」
「いよいよ、異い
な仰せかな。仙洞せんとう の法皇ともあるおん方が」
「お疑いも無理はないが、木曾が叡山に陣し、平家が途と
を失うて、昨日今日のあわて振りは、ここにいても、はや御存知でおわそうが」
「洛中騒動の有様は、山上にも頻々ひんぴん
と、聞こえてはおりますが」
「では、院のお立場も、およそは、お察しできましょう。じつを申せば、平家は一たん都を捨てて、後日、再び上洛じょうらく
を遂げんものと、昨夜来、一門退去の逃げ支度にかかっておる。主上はもとより彼らが掌中しょうちゅう
の珠たま 、併せて、法皇のおからだをも、西国へ奉ほう
じ参らせんと、かねがね、宗盛殿との間には、御黙契もっけい
もあったらしいが、院の御真意は、そこになく、はやくより平家をお見限り遊ばしておられたのです」
「さては、それゆえの御潜幸ごせんこう
でしたか」
「もし六波羅にさとられてはと、お側近くの女房たちや、日ごろ御腹蔵なき近習きんじゅう
たちにさえお告げなく、法住寺殿ほうじゅうじでん
を忍び出られ、途中、資時がお馬の口輪くちわ
をとり参らせて、虎口ここう を脱だつ
して来たわけです」
「おお、まことや、よくも危うい虎口を」
もう疑う余地はない、覚日も、やっとうなずいた。いや、どこかで 「わが意を得たり」 としているような語調でさえあった。 |