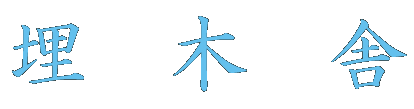先は十数騎。頼盛の多勢に適
うはずもない。すぐ馬首をめぐらして逃げ出した。 「池殿、寝返ったり」 「池殿には味方へ弓を引かれたるぞ」 と、大声揚げながら逃げて行った。
「追うな。追うな。こなたは、先を急がねばならぬ」
郎党たちへ言って、頼盛は一そう焦心あせ
り気味に駒を早めかけた。
すると、今の瞬間を、暗然と傍観していた老臣の平たいらの
宗清むねきよ が、
「あ。しばらくお待ちを」
と、駒を飛び下りて、頼盛の馬の口輪を抑えた。
「急ごうとは、そも、いずこへ急ぐ思し召しですか」
「宗清。なぜ、それを問うのか」
「お糺ただ
しせずにおられませぬ」
「わしの心を ── この苦しい、やりばのない気持を ── たれより深く知ってくれる者は、宗清、そちではないか。そちとのみ思うていたに」
「さればこそ、もう一度の御堪忍ごかんにん
を、たって、お願い申すのでおざる。今日までの、人知れぬ御忍苦も、ここで我慢をお破りなされては、なにもなりますまい。可惜あたら
、命惜しさに、御一門を見捨てた卑怯者ひきょうもの
と、世に口汚く言われましょう」
「いわばいえ、人の口端くちは
など、心にはかけん。頼盛が心底は、神仏が知っている。亡き母の池ノ禅尼ぜんに
、亡き義兄あに の太政入道殿
(清盛) には、分かっていて下さろう」
「さまで、おん二方ふたかた
の御遺志をお忘れないならば、なおさら、ここはもう一つ、歯をくいしばっても、自我にお克か
ちあらねばなりますまい。今し、主上を始め奉り、ご一門零落れいらく
のまぎわに、踵きびす を回かえ
して、ひとり都に居残られ給うては、多年のお志こころざし
も、むなしきばかりか、世の笑いぐさ」
「いやいや、わしは恥じぬ。この、みじめな路頭ろとう
の迷いを見たくないばかりに、早くより今日を憂い、鎌倉殿(頼朝) との仲を、なんとか、未然に和してゆきたいものと常々心をくだいてきたのだ。・・・・そ、それをば、あの、おろかなる内大臣おおい
殿はともあれ、一門のたれ一人とて、知ってはくれぬ」
「存じております。たれ知らずとも、宗清は」
「そうだ。・・・・二十余年前、平治の乱のあと、美濃路みのじ
にて、まだ十四の頼朝殿を召し捕らえ、わが屋敷へひいて来たのは・・・・宗清、そちであったろうが」
「はい」
「わが母、池ノ禅尼が、敵の子ながらあわれと思し召して、義兄あに
の清盛殿に、再三の命乞いをなされたの。・・・・そのため、ゆるされて伊豆の蛭ひる
ヶ小島こじま へ流さるるその日まで、頼朝殿に侍かしず
いて、手厚い情けをかけて与えた者も、わが家の弥兵衛やひょうえの
宗清むねきよ であったろうが」
「まこと奇く
しき御縁でした。およそ今日、平家と源氏の間に、なお、一縷いちる
の繋がりと、心の通いを望むならば、ただその一事しかございますまい」
「幸いに、鎌倉殿は、旧事を忘れず、禅尼の命日には供養を怠らぬと聞くのみか、その禅尼の実子なるがゆえ、この頼盛へも、四時の便りをままよこされた。──
身を平家一門におき、一門の者へ密ひそ
か事とは思いながら、平家源氏の確執かくしつ
が、けわしさを加えるにつけ、われ一個のみは、憎み合わぬ外に在って、なんとか、大乱にいたらぬように、また、万一の切迫せっぱく
には、鎌倉殿との間に立って、平家の崩壊くずれ
も、平家の面目と余命を保ち得るかぎりにおいて、事を、収拾せんものと、人知れず、ちぢに胸をいためていたのだ。・・・・そうした頼盛の本心は、家人けにん
にも、今日まで、明かしてはいなかったのが、そちには言わず語らず分かっていたはず。・・・・
「分かっておりまする」
「ならばなぜ、分からぬ一門の者のごときことを、そちも言うか」
「御一門の内に在ってこそ、御苦衷も生きましょうが、ひとたび、平家を離れては、今日までの御忍辱ごにんく
、すべて、水の泡でおざろう。いや、どうお言葉を尽くしても、池殿こそは、命を惜しんだものと言われまする」
「おお、命こそよ。内大臣おおい
殿どの のような愚物の麾下きか
に従うて、西海の果てに漂い、家の子郎党を死なせ、わが一命を終わるなど、思うだに、身の毛がよだつ。・・・・平家の滅亡は、あと幾年いくとせ
を待つまい。もう頼盛の願いも絶えた。わしはわしだけの願う道をたどる」
「では、どうあっても・・・・」
宗清は、さんぜんと、涙をたれ、
「もう申しませぬ」
「言うな」
と、鋭く、後ろめたい自己の迷いも断ち切るごとく頼盛は言った。そしてその焦心あせ
りを馬のたてがみにも見せながらすぐ駆け出した。
どこを頼みに、彼は、これだけの大家族を連れて、燃ゆる都のすみに、隠れようとするのか。
先々も、心細くなって、
「今は、身を託す主君にあらず」
と、考えた家来もあろうし、また、
「おれは根からの平家の子。主人たりとも、平家を離れ給ううえは、主人とは仰げぬ。──
あくまで、御一門の人びとと終わりをともにせん」
と、誓う者もあったろうし、故郷の田舎へさして帰った者も多かったに違いない。
やがて、頼盛は、京の外々そとそと
をまわって、仁和寺にんなじ 附近の一院へたどり着いたが、三百余の同勢は、わずか六、七十人に減っていた。郎党のあらましは、一門を見捨てた彼を、また見捨てて、途中、思い思いに影を消していたのであった。
|