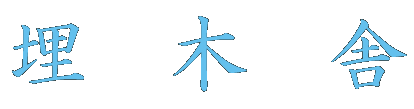八条室町
の池大納言いけのだいなごん 頼盛よりもり
の館も、その朝、たちまち、黒煙くろけむり
をあげた。
しかも、他のどこよりも早かった。
「わが家を焼いて落ちるに、人の手を借りることはない」
一族三百余人をまとめて、住み馴れた門を立つさい、頼盛が命じて、みずから火を放か
けて出たのである。
それには、老臣の弥兵衛やひょうえの
宗清むねきよ が、
「家々のお始末は、内大臣おおい
の殿 (宗盛) のお手勢が、時刻をはかり、時をひとつに焼き払うお手はずの由と伺っておりまする。時も来ぬ間に、身勝手な火を放っては、また、御一門の違和いわ
の因もと にもなりましょうに」
と憂わしげに、いさめたが、頼盛は、きき入れなかった。
いや、宗清が
“違和” と言った言葉の端が、かえって癇かん
にさわったらしく、
「宗盛殿は、じたい人も知る大ばか者じゃ。木曾を眼のさきに見て、腰をぬかしたも無理はない。・・・・したが、門脇殿かどわきどの
や経盛殿までが、うろたえにまかれて、都を逃げ捨つるとは、何事か。一門みな狂気したとしか思われぬ。狂人の令れい
だ、そんなものをこの期ご に守っていられようか」
いつにない激語だった。
ものに感じやすい眉、蒼白そうはく
な血相、常のお人とも見えない。
「無理ならぬお胸」 と察するかのように、清宗は黙ってしまった。
つい前夜まで、頼盛一族は、木曾の防ぎに、山科やましな
へ出兵していたのである。ところが、夜半ごろから他の同族が、続々、洛内へ引き揚げるので、糺ただ
してみると、主上を奉じて、一門西下の令があったという。── が、頼盛へは、全く沙汰なしなのだった。
「またしても、われを継子扱ままもあつか
いに」
そのときも、頼盛は、宗盛の狭量をののしって 「余りな仕打ちぞ」 と、怨うら
んだ。
木曾の大軍は都入り寸前の態勢にある。── 頼盛の立場は危険きわまるものだった。
── 前門ぜんもん
に虎とら 、後門こうもん
に、狼おおかみ といった形の中にあった。彼が、自暴自棄的な不平を口走るのも無理はない。
老臣の弥兵衛やひょうえの
宗清むねきよ は、それで、夕べから頼盛の心をなだめ通しなのである。
急遽きゅうきょ
、山科から帰るやいな、主家の妻子から女房たちまでを、牛車に乗せ、何一つ持つ物などはおろか、嘆き合うひまさえなく、せつなの大地震に逃げ出るような退去を余儀なくされたのだった。
門を離れるやいな、うしろに黒煙が揚がったので、牛車の中の女子どもは恐ろしさに泣き怯おび
えた。
頼盛は、子息の仲盛、光盛、為盛、妹婿いもとむこ
の少将しょうしょう 公衡きみひら
、むすめ婿の参議基家さんぎもといえ
、そのほかとともに、馬をそろえて、なだれ出たが、
「泣くな、泣くな、頼盛もおる。一族、みなひとつ道ぞ」
と、女車を気遣きづか
いながら、何度も叫んだ。
しかし、家の門へは、名残を惜しむ色もなかった。それへ憎悪すらもった。一刻も早く、不幸な半生の古巣を一炬いっきょ
に託して、何もかも忘れ去りたいような焦躁しょうそう
に、その姿は追われていた。 |