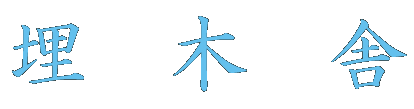いわば総領役
である。総大将の当然な任でもあった。宗盛は、最後まであとの六波羅に踏みとどまった。
一門眷族けんぞく
の落去らっきょ を見とどけたうえ、平家二十年のすみかを、きれいに、焼き払って去ろうがための、しんがりであった。
そのため、手勢五百をそばにおいて、彼の一陣は、馬場の馬冷うまひ
やし場ば (池)
のほとりにたたずみ、輿こし 、牛車、人馬などの奔流が、あとを絶つのを待っていた。
「もうよかろう。あらかじめ、布令ふれ
てもある。もはや、火を放っても、屋や
のうちで、焼け死ぬ者はあるまい」
気の長い宗盛であるくせに、いまばかりは、気みじかに、幾たびも言う。
広い馬場の東口と西口に、背の高い馬道門がある。淡路守清房の影が、西の屋根の上に見え、東の屋根には、宗盛の子、右衛門督うえもんのかみ
清宗がのぼっていた。
「まだです。まだまだ、人びとの流れや牛車の影は、絶えませぬ」
清宗が、大声で伝えると、西の屋根でも、清房が、手を振っていた。
「遠方此方おちこち
の門々には、なおまだ、去りがての人影だの、馬のいななきもしております。── 東大路や大和大路の混雑も、すこしも減っておりません」
宗盛の耳には、その声さえ、虚空からする呵責かしゃく
のムチに聞こえた。
父がきずいた平家二十余年の府を、このように崩壊させ、一門を路頭に迷わせてしまったのも、責めは、自分にある。暗愚な総領のせいだと世に言われても仕方がない。
だが、と宗盛は心の内で言ってみる。
自分が、父清盛や兄重盛にまさる者とは、かりにも思ったことはない。自己の凡庸ぼんよう
をよく知って分ぶん を守ってきたつもりである。
一門の運命を負い、四面の敵に抗して、多難な時流に克か
ってゆける自分でないことは、たれよりも、自分が一番知っている。さればこそ、法皇へは、努つと
めて恭順きょうじゅん に、内輪事はなるべく穏便に、そして境外の敵に対しても、われから積極的に討伐を企んだことはなく、ひたすら防衛を主として、ただ、事なかれと祈って今日へ来たのであった。
ところが、願いはすべて、くつがえされ、時局は逆に、平家の瓦解がかい
を、急にした。
外戦、内政、みな非である。法皇すら、まんまと、平家のウラをかいて、姿を消し給い、一門の中にも、池頼盛のような、二心を抱く者もいて、君王も肉親も信じられぬような、不安と猜疑さいぎ
が、お互いの心を吹きくるんだ。そうした昨日今日こそ、地獄そのものではないだろうか
「焼こう、一切を焼いて、立ち退の
こう。── 敵に利をくれぬためにも、また、後ろ髪の思いを断つためにも」
かなたの馬道門の上へ、宗盛はまた、もどかしげな眼をやった。屋根の人影は、なんの合図もまだ見せない。
「・・・・むかし、父禅門が、この地を開き給わぬ前は、ただ野水や葦あし
ばかりの、淋しい六波羅野であったという。火をかけて、もとの荒寥こうりょう
たる枯野にもどし、去って、福原の父の墓所にぬかずこう。不肖の子の力及ばず、こう成り果てた次第を、ふかくお詫わ
びせん。・・・・口惜しさは、かぎりもばいが」
身を床几しょうぎ
にかけたまま、彼はいつか、落涙していた。あたりの将士のてまえもなく、しきりに両眼を指でぬぐった。
すると、門屋根の上で、
「もう、火を放つも、よろしいでしょう。総門道は、五条の橋づめまで、東の大路は、松原の南の端はず
れまで、人馬の影も、まばらとなりました。幾千軒の下にも、はや、人がおるとも見えません」
手を打ち振って、そこの清房も言い、一方の清宗も合図していた。
宗盛は、われに返って、左右の侍大将に、かねて示しておいた二十箇所の家々へ、一せいに火を放てよと命じた。
無数の松明たいまつ
に火を点じ、手に手にそれを振りかざした兵馬の影は、辻々を東西にわかれてゆき、やがて京中に放火し始めた。みずからの古巣をみずからの手で、惜しみもなく、焼き尽くして行ったのである。 |