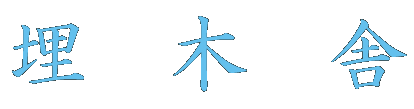まず第一に待たれたのは、摂政
基通もとみち の姿であった。途中でたしかに見たという人びとも多いのに、どうしたのか、まだ着かない。
いや、それよりも、困ったのは、一門の総領であり、全軍の総大将である前内大臣さきのないだいじん
宗盛むねもり が、見えないのである。宗盛がいないでは、どうしようもない。はやくも、主上の御輿みこし
と、内侍所ないしどころ の唐櫃からびつ
など、初秋の風光る中に、行き暮れ給うお姿であった。
── その西風の吹いて行くかなたに、人びとはややもすれば、しぐ心をひかれ、眼をふり向けた。
都、都、住み馴れたあの都。
今日さっていつ帰るとも知れぬ都。
ここに立った一人一人には、身につながる愛いと
しい人も、別れ難い老父母も、幼い子らも、みな、足手まといとして、そこに残して来たのである。
「どういして、この先を、あすを、生きて行くやら」
別れたたれかを、想っていない眸ひとみ
はない。
すると、その眸に、かなたの遠い炎が映った。洛中の屋根の上からである。やちまち、大きな黒煙をともない、見る間にそれは、巨大な火の柱になって、朝の陽ひ
を暗くし出した。
しかも、一箇所や二箇所ではない。
六波羅の空、西八条の空、そのほか、京中二十余箇所から、前後して、えんえんと、燃え揚がって来たのである。
「おおっ、お味方の手で、火が放つ
けられた」
「立ち退くからには、後に一物もとどめまいぞと、前もってのお布令ふれ
ではあったるぞ。その火は、あれか」
「あわれ、六波羅、池殿、小松殿、八条、西八条なども、いまは塵ちり
芥あくた のごとく、焼き払われているぞよ」
「おれどもの家々も、あの火の下であろう。無残やな、無常むじょう
やな」
「でも、、おのが住家すみか
を、木曾のやつばらに、思うままにされるよりは」
「さはいえ、悲しいぞよ。どう思っても、悲しいことだ。あの美しい都が消えて、ただの焼け野原になるかと思えば。そして、ついゆうべまでは、妻子とともにいた家も焔ほのお
になっているかと思えば」
兵は、手放しで泣いた。みな、頬を涙で濡らしたまま、茫然ぼうぜん
と、われも忘れている。
まして一門の公達は、いうまでもない。哀惜の涙には、無念がこもった。清盛の在りし日を思い、その苦闘と建設と栄えにいたるまでの過去を、平家とともに生きて来た年長者には、なお、たまらない苦痛だったにちがいない。自らの手で、自らの身を、生きながら火葬に附している思いであったろう。
「やあ、分かった。内府殿の遅いは、あの火放ひつ
けのせいじゃ。手落ちのなきよう、あとの芥焼あくたや
きを、おさしずしているためであろう。追っつけ、馳は
せ参られるにちがいないわさ」
修理大夫経盛が、馬上で言った。
亡き清盛のすぐ下の弟である。六十一歳ともなると、これほどな悲痛さにも、あさいて感情をつかれないものか、彼のみは涙もせず、といって、猛気に駆られた風でもなく、日ごろ、和歌や笛の話をする時のような温顔のままで、人びとへそう言っていた。その、低めな経盛の声が、遠くにまで聞こえたほど、喧騒けんそう
も混乱も、ひそとして、渚なぎさ
の水音だけがそこにはあった。そして数千の将士は、ことごとく、ふたたび夜に返ったような空に向かって、黙然と、両の掌て
をあわせていた。 |