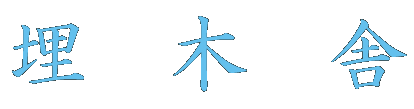六波羅の大路
小路こうじ 、あなたこなたの目路めじ
目路めじ には、その夜明け前、幾万の男女や老幼の涙がしぼられていたことか。
暗いうちに、軒ごとの家族らは、別れを惜しみあい、すべて、家を去らねばならなかった。
戦いうる者は、軍勢について、西国へ落ちて行く。戦う力のない老幼や女たちは、いずこえなと、寄る辺べ
を求めて、立ち退の けという布令である。
悲泣ひきゅう
、哀号あいごう の声は、未明の闇をなお暗くし、墨のような朝は、なかなか明けようともしない。
「やあ、すこし道を開け、道を
── 。余りに立ち乱れるな。主上のおわたりぞ。行幸みゆき
なるぞ。馬の群を、たたずますな。そこらの馬を、どこかへ片寄せい」
かなたから駒こま
を飛ばして来て、こう軍勢の上へどなって通ったのは、右近衛中将うこんのえちゅうじょう資盛だった。
道に立ち、門を塞ふさ
ぎ、辻々にあふれ返って、たふぁ揉みゆれていた兵馬の海は、ようやく、路面の見える程度に端へ寄った。
やがてまた、権中納言ごんちゅうなごん
知盛とももり が 「しっ、しっ」
と、道の露を払って先駆さきが
けて行く。── ほどなく、主上の御乗物が、星の下に見えた。御車ではなく、御輿みこし
であった。
輿こし には、おん母建礼門院が、ひとつに、乗っておられた。幼帝には、この出でましを、どんなお気持で、おん母のひざに抱かれておいでだろうか。
にわかに、お眠い中をゆり起こされて、さだめし、だだをこね、おむずかりもして阿波あわ
ノ局つぼね や帥そつ
ノ局つぼね の手をやかせたことであろう。それもおん母の、せきあぐる涙をしげくしたことにちがいない。
けれど、御輿が、星の下に出ると、すっかり、お眼がさめた御容子である。兵馬の大群も、おめずらしげであり、乗らせ給う御輿を舁か
く八人の雑色ぞうしき 、紅白の縒綱よりづな
をひく御綱佐みつなのすけ たちの、弓矢、よろい姿ななどに、喜々として、何か、おん母へ、戯ざ
れかけていらっしゃる。
ひとまず、御輿は、六波羅泉殿に内へはいった。あわただしい御朝食の供御くご
があった。またそのまに、平大納言時忠が、子息や大勢の家臣を連れて、この場へ、遅く駆けつけて来た。
彼は、主上の仮の宮居みやい
から、神璽しんじ 、宝剣ほうけん
、八霊御鏡やたのみかがみ 、朝廷の正印、鍵、時の簡ふだ
、玄象げんじょう 、鈴鹿すずか
の御琵琶おんびわ など、およそ、皇室にとっての重代の宝物塁を、取り出す役目に当っていたのである。
けれど、何ぶん、火に負われるようなあわただしさであったので、神庫の口で、取りこぼしたり、持ち忘れた品々も少なくはない。
たとえば、つねに清涼殿せいりょうでん
に置かれる “昼ひ の御座ぎょざ
の御剣ぎょけん ” なども、このおり、どこかへ失っていたという。
が、ともあれ、三種の神器、そのほかは、唐櫃からびつ
は、甲冑かっちゅう 弓箭きゅうせん
の荒武者どもにこれを守らせ、二人の子息、内蔵頭くらのかみ
信基のぶもと 、讃岐さぬきの
中将時実、そして時忠自身も、衣冠を着して、その列の加わった。ほどなく主上の御輿みこし
は、泉殿をお立ちになり、神器を捧持ほうじ
する一群も、しのおん後から続いて行く。── 六波羅大路から西へ、朱雀を南へ ── 行幸みゆき
とはいえ、果てない亡命の御旅路に従って行くのであった。
主上の御先発を見とどけた後、一門のたれかれやら眷族郎党けんぞくろうとう
など、以下続々と、ひきもきらず、六波羅を立ち退きはじめた。
時に、卯う
ノ上刻 じょうこく (午前五時)
ごろ。
まだ道はうす暗い。中天には、銀河 あまのがわ
のあとが、夢のようにほの白く仰がれる。この朝を境に、秋も、どっと駈け降りて来た。風は冷たく、路傍の虫たちも草むらに声をのんで、露ばかりが、都じゅうの涙のように光っていた。 |