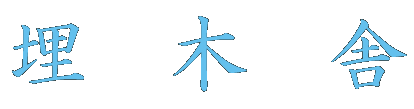彼に従って門を出た一群の歩騎の人影は、その足で、ほど遠からぬ法住寺殿
の森へ急いだ。
主上、女院とともに、法皇後白河にも、同様な御退去を願って、西国へ供奉ぐぶ
しようという宗盛の方針は、だいぶ前からの考えであったようだ。その夜の一門最後の評議でも 「主上、法皇のおん二方さえ、味方の内に取り奉れば、源氏は、天下に令するなんの口実も持ち得ない」
として、都を捨てる前になすべき、焦土作戦しょうどさくせん
の眼目としていたのである。
ところが。
院の御所、法住寺殿は、その時刻ごろ、すでに、もぬけの殻だった。巨大なる空巣となった大殿おおどの
や萱かや 御所、そのほかの建物の内、どこにも、後白河のお姿はお見えにならない。
「や、や。院には、いつのまに、いずこをさして」
法皇御逐電ごちくでん
と覚さと ったとき、宗盛は、体の筋を抜かれたように、呆然ぼうぜん
としてしまった。そして、呻うめ
くが如く、
「下司げす
のごとき奸智かんち をもって、まんまと、われらを欺あざむ
き給えるよ」
と、口の内でののしった。
いま、思い合わせると、十日ほど前、院の近臣宗時をつかわされて 「危急の場合は、どうする所存か」 を、宗盛へ密々におたずねがあった。
正直に、宗盛は、西国落ちの意中をお打ち明けした。その後とて拝謁はいえつ
もしているし、また、院中の軍議も行われていたのである。そして、そんな御不同意な容子はお示しになっていなかった。気の言い宗盛は、すべて、おふくみのうえ、自分たちに御同意のものとばかり、今が今まで、ひとり決め込んでいたのである。
要するに、後白河は、平家のウラをかかれたのだ。今ごろはどこかで
「迂愚うぐ なる宗盛よ」 と、笑っていらっしゃるにちがいない。
だが、迂愚なる宗盛は、それでもなお、自分が出し抜かれたとは思い切れないらいかった。いつまでも、その血相をたぎらせて、
「なお、隈くま
なくお尋ね申せ。宵にはまだ、しかと、御所におわしたはずなのだ」
人は探し出せたが、それは、下部や蔵人くろうど
たちであった。また、日常、御前に奉仕する小女房などが、局々つぼねつぼね
から、引き出されたにすぎない。
それらの者を、ひとまとめに、庭上にすえ、宗盛みずから、きびしく問いただした。
「なんじらは、知りつろう。院には、そも、いずこへ御幸ごこう
なされたぞ。申せ。御幸のお行く先を」
しかし、何を問われても、
「ぞんじ上げませぬ」
彼女らは、顔を振るばかりだし、蔵人や下部の輩やから
も、
「いっこうに、何事も存じません。もし、御幸がほんとなら、よくよく、お密ひそ
かにお出ましになったものでしょう。── 御寝ぎょし
にはいらせ給うた後は、なんの御気配だにうかがわれませんでした」
と、口をそろえて、いぶかり合うだけである。
院の仕つか
え人びと までが、真実、こう知らないほどならば、法皇の御逐電は、いよいよ御計画的なものだったにちがいない。
宗盛は、今さらのように、地だんだ踏んで、口惜しがった。
しかし、捜査の手を分けて、お行方のあとを追うにも、いかんせん、もう時間がない。一門都落ちの大きな手順は変えようもなかった。
宗盛は今ほど虚無うつろ
な天地を感じたことはない。この夜も常と変わりなく祇園精舎ぎおんしょうじゃ
の鐘は、寅とら ノ一天
(午前四時) を告げている。暁闇ぎょうあん
はまだ濃く、星はあざらかだが、はや、明けて七月二十五日であった。この日をもって、一門ひとり残らず都を捨て、西国へ落ち行かんと、ゆうべの評議は決まったのだ。天は傾く平家に、今は時さえ貸さぬのかと、彼は、むなしく六波羅ろくはら
へ引っ返した。 |