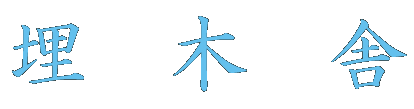言葉や観念の上では、騒いでいても、二十余年の栄華と無事に馴れた平家の人びとには、ほんとの大乱とか危機とかは、まだ、真に身に分かってはいなかった。
西国の不穏、東国の異変、近畿の無秩序と、近年、頻々
たるものを見ながらも、なお、なんとか片づいて来た安易さが、その不安をも麻痺まひ
させ、自負心をも慢じさせて、何が起こっても、おおむね、驚きもしない習性をいつか身に持ってしまったのではあるまいか。
しかし、こんどばかりは、さしも宗盛以下、悠長ゆうちょう
な人びとも、眼をさまして、
「いかに木曾を追いしりぞけん。かくては、都の守りすら?」
と、肚はら
の底から、恐れを抱いた。そして、余りにも急速な義仲の進出に、まったく、施すすべも知らなかった。
とはいえ、全然、なすなくいたわけでもない。一門の者は、日夜、宗盛を中心に、ひたいを集め、
「いかにすべき」 を、議していたが、それがまた、公卿衆議に似たようなもので、
「ああ、かかる日、せめて、小松内府か、入道禅門なりと、ましまさば」
と、いたずらに、亡き人の德や力の大きさを、今さら、偲しの
んでみたりするだけだった。
さきに、院の後白河からは、
(鎌倉と、和睦わぼく
してはどうか。頼朝にも、その気持はあるように思うが)
というお扱いもひそかにあったが、これには、一門あらましが、反対であった。
宗盛、頼朝の源平二巨頭が、ひとつ都で、並立してゆけそうもないし、かたがた、池頼盛に対する疑惑と反感にも、根強いものがある、頼朝といえばすぐ
── 池殿が介在してのこと ── と疑いはまず頼盛へ向けられる状態だった。
だから、一門集議のばあいでも、頼盛はめったに、発言したためしがない。
もの言えば、その唇くちびる
へ、同族たちの疑いの眼を招き、席にも耐え難い針のむしろを感じるからであった。── といって、殻を固持しているような沈黙も、すがすがしいものではない。
ために、この際ながら、頼盛だけは、集議にもよく欠けていた。病やまい
といって、引き籠りがちだった。そのほかは、宗盛を主座に、教盛のりもり
、知盛とももり 、経盛つねもり
、経正、重衡しげひら 、忠度ただのり
、清宗、維盛これもり 、資盛、通盛みちもり
など、一門の公卿武将、何十人ろなく、朝に夕に、六波羅を、あわただしく出入りし、寄り寄り、策をこらさぬ日はなかった。
そのあげく、平家側でも、 「叡山を敵へまわしては」
ということに気づいた。
もっとも、叡山の首脳部でも、密々の動きはあった。
故入道と生前の誼よし
み深かった明雲座主ざす なども、院の側近に対して、
「木曾と平家とを、和議さするように、このさい、法皇の御院宣なと降くだ
し給わらば」 と、裏面で、働きかけた形跡がある。が、後白河には、どうお考えか、こんどは、なんの御意志も表示なさらない。そのまに、日は過ぎて、ついに木曾きそ
牒状ちょうじょう への叡山えいざん
返状へんじょう は、義仲の許へ送られていたのである。
平家一門連署の誘い状
── 「山門、平家方に味方あらば、平家は長く山門を氏寺うじでら
とし、一族天台に帰依きえ せん」
という誘いが叡山へはいったのは、七月五日付けの書状であった。時すでに遅し、である。義仲と山門との密約は、それより三日前にもう結ばれていたのである。
しかも、末路に瀕ひん
した人びとは、
「やがて、よき、答えみやある」
と、首を長くして、その返答を待ちぬいている迂遠うえん
さである。
ただ、その間にも、いささか、一門の人びとの意を強うさせたものは、おなじ七月十四日、かねて西国へ出征していた一族の肥後守ひごのかみ
貞能さだよし が、原田党、菊池党、松浦党などの九州平家三千余騎をひきつれて、めでたく、凱旋がいせん
したことであった。
それらの武将のものがたりには、
「たとえ、北陸、東国などは、どう、人の心変わりもあれ、西国においては、なお、平家恩顧のともがらも多く、平家の領家領国は、ゆるぎもしませぬ」
と、たのもしげに聞こえたので。
「さもあらば、なじか、義仲ごときを」
と、宗盛なども、にわかに、天下の広さを思い直し、もし、叡山が積極的な味方もせず、中立的な態度に出ても、義仲と雌雄しゆう
を決せん、と肚をすえていた。 |