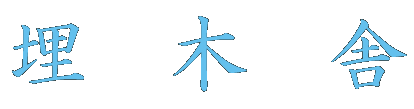そして、彼はまた、食える草木を、諸書にわたって調べてみた。木の実、木の皮、雑草、およそ生きるための糧
なら、牛馬、野鼠、鳥虫、何でも食えることを知って、意を強うした。 「試しに」 と、蟋蟀こおろぎ
を食って、ヘドを吐いたりした。
妻の蓬よもぎ
は、
「オオ、いやだ」
身ぶるいして、
「あなた、気が狂ったのじゃないでしょうね」
と、半ば眼を涙ぐませた。
「ああ、正気だよ」
「もとから変わり者で、物好きな、あなたでしたけれど、このごろはまた、ほんとに、正気かしらと思ったりしてしまう」
「天候も変だし、世の中も変だしするから」
「ですから、良人のあなたぐらい、しっかしていてくださらなければ」
「女女房は、心細いというのかい」
「だって、草を食べたり、虫を食べたり、それでこの間も、お医者のくせに、おなかを下痢くだ
したりしたじゃありませんか」
「いまに、おまえだって、鼠ねずみ
でも、木の皮でも、食べ始めるにちがいない。そして、吐きもしないし、おなかも痛むことはなくなるよ」
「ま、あなたは、どうしてそんな、いやな取り越し苦労ばかりするんでしょう。いくら飢饉ききん
だって、もう、今年をしのげば」
「その今年が、危ないな。飢饉だけなら、まあいいがね。人間が人間を食いあうようなことにならねばよいが」
「そう、そう」
蓬は、ぞっと、何かを思い出したように、
「ほんとに、あるんですってね」
「なにが」
「人間の肉を食べた人間が。そんなことを、近所の者が言っていましたよ。なんでも、河原で見た者があるんですって」
「嬰子あかご
をか」
「そうですって」
「あわれだなあ・・・・元来はみな善性の人間なのに」
「それにまた、やたらに、捨て子が多いんですとさ。このごろは」
「拾ひろ
い人て もありはしない。いったい捨てられて子は、どうなるんだろ」
「どうもなりはしません、泣な
き死じ にに、死んでしまうほかは」
・・・・蓬。どうだろう。わしたち夫婦で、そうした捨て子を、拾って育てようじゃないか」
「え?」
「いやか」
「拾いきれる数じゃないんですよ。だからあなたは、すこしどうかしたんじゃないかしらと、ときどきわたしは心配になるんです。だいいち、そんなたくさんな捨て子を、どいうやって育てるつもりですか」
「どうなとして」
「御自分さえ、蟋蟀こおろぎ
を食べてみたりしている矢先に」
「・・・・ああ、どうにか、ならぬものかなあ。いかに凶年つづきでも、都の内には、なお、あまたな御館おやかた
の門もあり、社寺の大屋根もあるものを」
「いくら、身をもがいて、そんなことを仰っしゃったって」
「じゃあ、おまえがもし、飢えて、死にかかったら」
「いくら飢えたって、子は捨てません」
「そして」
「一緒に死にます。抱き合ったまま、親子一緒に」
「それだけのことなら、犬猫いぬねこ
の親子でもするよ。それだけじゃあ、扶たす
け合あ いにはなりはしない。人間の世の中らしい相すがた
ではあるまい」
こういう相談になると、彼と妻の間では、埒らち
があかない。彼女の理解の外だった。母としても妻としても、家の垣とおなじに、ある限界がある。
蓬にすれば、良人はのんきな人だと思う。きのうの辻は、ひと事どころの騒ぎではない。
なんでも、うわさには、木曾殿の軍勢が、もう近江の国へ入って来たとやらで、京中かなえ・・・
が沸わ くように、ごった返しているではないか。
そして、人の言うには、
「木曾は、山家やまが
の、猪武者いのししむしゃ ばかり、情なさ
け容赦ようしゃ を知る者でなはない。北陸でも近江でも、女という女はまいな手籠にされたぞよ。平家に出入りした輩やから
は、市人いちびと でも殺されよう。木曾鬼を、都に入れるな。木曾鬼を都に見たらこの世の終わりだぞ」
嵐の先駆さきがけ
けのように、伝わってくる。
また、それとはおべこべな風説もあって、
「逆悪平家がつぶれ、木曾殿が、都入りあれば、世は、たちまち楽土になろう」
と、いう者もある。
どっちが真か、どう違うのか、庶民には分からない。
分からないままに、恐怖はつのって、まったく、この世の終わりかと思わせるような世相を呼び起こした。食もなく、安き眠りもない暗澹あんたん
たる都に、一日もいたたまれない気にも駆られ、争って、家財道具を山野へ運び始めたのである。
下層だけではない、上もそうだった。
この洛中上下のうろたえは、平家の北陸大敗が緒ちょ
だったのはいうまでもない。でもなお、半信半疑ではあった。ところが、前後して都へ逃げ帰って来た平家勢の姿を眼に見るにおよび、収拾もつかない状態に陥ったのである。──
それが六月末から七月初めのことであり、やがてまた現実に、木曾勢が叡山の上に現れ、義仲が、その本営を東塔総寺院へ置くにいたって、洛内の様相は、破滅寸前のけわしさを表面化していたのである。
義仲が立った叡山東塔の辺からかなたを俯瞰ふかん
すれば、一片の雲もない夏空の下、飢餓と恐怖にくるまれた下界の一区域には、右往左往の蟻地獄ありじごく
そのままな騒ぎが、手に取る如く彼の想像にのぼるのだった。 |