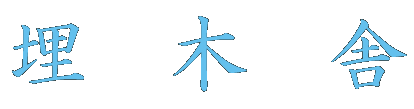いつか山ふところの襞
は、紫ばんだ暮色を抱きはじめている。倶梨伽羅の山の肩は、夕焼けに染め残され、山風は、急に冷たくなってきた。
すでに、中黒坂の上りだった。歩一歩と、足もとは暗くなる。
するとふもとの方から、しっ、しっ・・・・という妙な声が聞こえ、一団の鈍重な部隊が、山坂を追い上げて来た。何百頭か、数も知れないほどな牛だった。民家の農牛、牧の野牛、隊の荷駄牛にだうし
など、あらゆる所から狩り出してきたものに違いない。
不気味で鈍間のろま
な牛の大群も、やがて山腹の平地に寄せられたり、山上に近い木立の中に隠されて、天地は依然、静かな雲のたたずまいと、うっすら、木の間もる宵月の影だけだった。
「音な立てそ。声な揚げそ」
将士は、戒いまし
めあった。
義仲のいる位置さえ、今は、見方の者にさえ、よく分からなかった。
「なお、何を待たれるのか」
士卒には、それも、合点がゆかなかった。
後に思えば、このときなお、義仲は、樋口次郎兼光の一隊が、北黒坂の途中から、さらに別れて、遠く、矢田山、九折つづら
、坂戸などの北の嶮路けんろ を迂回うかい
して、はるか平軍のうしろに出る時刻を、辛抱強く待っていたものらしい。
やがて、夜も二更にこう
をすぎたころ、はたして、遠い遠い螺ら
(ほら貝) と攻め鼓ゆづみ
が、山風のうちに聞こえて来た。
義仲は、草むらから突っ立って、耳をすまし、眸を、星にこらして、
「まぎれはない、あれは、樋口兼光、余田次郎が打つ攻め鼓ゆづみ
、合図の貝ぞ、者ども、今はよいぞ、木蔭からこぞり起た
てやい」
おうっという答えが、山腹のやみを一度に揺るがした。同時に、ここの陣でも、螺ら
を吹き、鼓こ を打ち、武者声をあげた。
鼓螺こら
の谺こだま は、さらに、南黒坂にも、北黒坂にも起こった。呼び交か
う嵐あらし と嵐にようである。そして、そのすさまじい旋風は、武器、よろい、馬具、人間のわめきを包んで、急速に、山上へと、駆けのぼっていた。
不覚にも、猿ヶ馬場の平家の陣営では、
「や、や、あれは」
と、降ってわいた事のように、四面の敵に仰天した。
昼の小ぜりあいに、やや優勢を示し、矢立山の木曾勢も、夜とともに、沈黙してしまったので、
「さしたる敵かは」 と、自陣も矛をおさめて、気をゆるめていたものであった
それに、矢田山、九折などの嶮は、踏み越えられる地形ではない。その方面は安全と、警固もしていなかったのだ。
「敵は、前後にあるぞ」
「いや、三方、四方」
「いたずらに、あわてふためくな。まず、卯ノ花山を前にとり、塔ノ橋をさかいに、撃って出よ」
十一日の月は雲間にあるが、物思わしいほど、ほの暗く、ほの明るい。
たちまち、鷲尾山と卯ノ花山のあいだ。また塔ノ橋、天池のあたりで、黒い夜霧が巻いているような両軍の接戦が起こった。
「きたなし、返せ返せ」
「ここに敗れて、京の人びとに、なんのかんばせやある」
「木曾は小勢ぞ、何を恐れて」
もう浮き足見せた平軍の中では、悲壮な叱咤が、しきりに叫ばれ、いたずらに多い大軍自体が、足場の不利に、その大兵力を持て余し、味方同士、ただ揉み合い、喚きあいの無秩序をいよいよ加えてしまうに過ぎない。
|