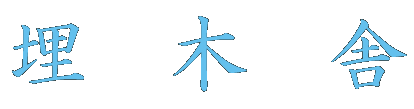およそ平家方四万を超
える兵数に、二万弱の木曾勢がぶちかったことを想像すると、砺波山の三道、山頂、ほとんど人馬で埋るばかりであったろう。暗さは暗し、道は狭いし、いかに戦ったかさえ、疑われるほどである。
そのうえ、」やがて、機を見ていた義仲が、
「放て」
と、さいごの一計を敵に加えた。
海野幸広と小諸忠兼にいいふくめて、にわかに集めさせた数百頭の牛を、平軍へ向かって追い放したのだ。
一頭一頭、牛の角つの
には松明たいまつ がくくりつけられてあった。火を見るやいな、その尻しり
を、兵がムチで撲りつける。牛は、焔ほのお
の角を振り立てながら、盲目的に、敵陣へ狂奔してゆく。
この光と怪物の影を見ただけでも、平軍は 「何事か?」 と胆きも
をすくめた。猛牛の群は人びとが 「あれよ」 と、身の処置を取るひまもなく、人馬の中に、割り込んで来た。
牛は牛と思えない迅はや
さと獰猛どうもう をほしいままにした。人間は踏み潰され跳ね飛ばされた。ただ動転どうてん
するだけで、それを支える一酬いっしゅう
の力もない。弓矢、長柄、太刀、甲冑かっちゅう
などは、すべて無用の長物だった。
東にも敵、西にも敵。
北には、嶮けわ
しい岩山。
しかも、急鼓きゅうこ
の響きは、全山をゆるがし、不気味な陣貝の音ね
は、雲を裂くばかりである。平軍四万は、戦うことを知らなかった。ただ、どう走るか、どこに拠よ
るか、身を伏せる何かでもないか。岩につまづき、馬は人を踏み、矢風に追われ、火に吹かれ、恐怖の怒涛どとう
を作って、さらにその恐怖の中に、全平家軍をまきこんでしまった。
すると、一群の軽兵が、猿ヶ馬場の東を指して、
「こなたぞ、こなたぞ。こなたは平地、足場も広い」
と、しきりにどなっていた。
「さては、退き口」
「神の助け」
と、兵軍のなだれは、先を争って、東へ向いた。ひとたび、よい退き口と見るや、後から後から、全山の平家勢はみなその一所を目がけて集まった。
押し合いヘシ合い揉も
み重なってゆく。それは、吐け口を得た濁流の勢いに似ていた。
理性の片鱗へんりん
も働かしえないかなしい人間の渦だった。洪水こうずい
の中の鯉こい 、鮒ふな
、どじょう、蛙かわず 、犬、猫、鶏の漂いとも、何の違いもない相すがた
だった。
盲目なその激流は、絶え間なく、限りなく、いくらでも続いて、後と断たなかった。
行きつかえるはずもない。行く手の先は巨大な奈落ならく
の口だった。いわゆる倶梨伽羅谷 ── 後世呼んで “地獄谷” とも駈込谷ともいう深い谷底だったのである。
谷にはそのころ、十余丈の滝があって、真下は、奔湍ほんたん
が逆まき、途中の断崖絶壁だんがいぜっぺき
には、いちめん、栃とち の木が繁茂していたという。
「あっ、た、た、谷間ぞ」
「道はないっ。道は」
喚おめ
けど、もがけど、この恐怖と狂奔の盲目が急に醒さめ
めるはずもなかった。人も馬も山つなみの勢いをなして、谷底へ落ちころげ、人馬の死屍しかばね
は積んで栃とち の断崖の半なか
ばを埋めたほどであったという。
古典平家では、このとき、倶梨伽羅谷に死す者、七万騎とあるが、それほどでないまでも、戦死一万以上はくだるまいとは後の史家もいっている。そして、その谷間から小矢部川へ落ちて行く水を、里人は、膿川うみかわ
と呼んだ。夏が来れば栃の若葉にも、秋来れば紅葉にも、地獄谷には四季、鬼哭啾々きこくしゅうしゅう
の声が聴かれると、後々まで言い伝えた。 |