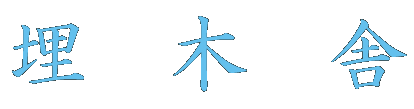すると、近くの木蔭をよぎって、社家
の裏へ、姿を隠した女房がある。女は、二人の子供の手をひいていた。
おや、というような眼をして、経正は、老禰宜へむかい 「どこかで、見たことがある女房だが」
と、訊たず ねた。
「いえいえ、お見覚えのあるような上臈じょうろう
ではございませぬ」
禰宜ねぎ
は笑う。また受けもしない。しかし経正には、どうしても、見たことがある気がする。どこかで、たしかに会っている。
余りに、彼が首をかしげるので、禰宜はあとから言い足した。
「貧しい薬師くすし
の家族でございますわい。はい、まことに、貧乏町の、名もない薬師で」
「はて。都の」
「もとは、牛飼町とかに、おりましたそうな」
「では、阿部あべの
麻鳥あさとり ではないか」
「えっ、御存知でございますか」
麻鳥ならば、よう知っておるが」
「これは、これは」
と、老禰宜は、言いすぎた口を悔いるように、そしていかにも、意外らしい顔をした。
どうして、麻鳥の家族が、ここに来ているのか。
聞けば、ここの老禰宜は、麻鳥の父阿部島彦の弟にあたる者だという。
その縁故で、麻鳥もまれにここへ訪うて来ている。そして参籠さんろう
がてら、妻子とともに幾日かを過ごして行くが、彼自身は、社家の一窓いっそう
で、何事にも煩わずら わされない読書三昧どくしょざんまい
の幾日かを、無上の楽しみとしているらしいということであった。
「経正なり、と申せば分かる。いまもおるならば、ぜひ会いたい」
彼の言葉に、禰宜は社家へ立って行き、まもなく、麻鳥を連れて来た。
麻鳥は、相も変わらず、葛布くずぬの
の粗末な袴はかま もしわのままに、経正を見ると、菅すが
むしろの外へ、小さくなって坐った。
「おう、やはり麻鳥どのだったな。奇しくも、ふしぎな所で会お
うたものよ」
「まことに、このような島で、思いがけのう」
「亡き入道清盛殿のおひきあわせでもあろうず。竹生島ちくぶしま
の神も、平家の氏神厳島も、弁財天女」
「何かは存じませぬが、世の流れ、人の移りは、もっと、奇妙でございますなあ」
「されば、西八条殿 (清盛)
がお亡くなりになった後は、わけて烈はげ
しく世も変り人も変わった。いや、われらも、その後は、沙汰を怠っていたが、あらためて、あのおりの礼を申すぞ。麻鳥よ。一門の者に代って、このとおり、お礼をのべる」
「あ、もったいない」
麻鳥はあわてて、手を振った。
「そのせつ、あなた様のお迎えをうけて、西八条の御病殿ごびょうでん
へ参上いたしましたものの、いかにせん、時すでに遅しでございました。ただお悼くや
みに伺ったような通夜つや 医者でしかございませぬ」
「いやいや、御辺の懇ろな診立てによって、二位ノ尼どのも、どれほど、おあきらめがよかったか知れぬ。われらも、後では、御辺の学説に、よく得心とくしん
がまいった。それにしても、御辺のごとき名医が、どうして、施薬院の官職も賜らず、貧しい町の片隅かたすみ
に朽ちているのか」
「いえ、どういたしまして、わたくしはべつに貧しいことはございません」
麻鳥は、すまして答えた。
それ以上は、笑って何も答えない。
老禰宜は、貴人に対して、この風変わりな甥おい
の不愛想ぶあいそ ぶりを、ひどく、恐縮顔だった。それを取りなすかの如く、麻鳥の身の上を、問わず語りに、経正へ話すのだった。
阿部家は、伶人の家で、麻鳥も若年までは、宮中の楽寮に仕えていたということ。──
そして、崇徳帝の退位とともに、柳ノ水の水守みずもり
となり、今でもまだ、その柳ノ水のそばに住んでいるということ。── そしてまた、医をもって貧民の友となり、生涯、医と水守みずもり
で暮らすのが、本望であるといっているということなどを。
「・・・・なにしろ、まことに、おかしな性さが
の男でおざる」
と、この叔父も、常々、あきれているらしく、いうのであった。
経正は、いちいちうなずいて、一そう麻鳥をゆかしく思った。そして、何を好んで貧乏しているかといった自分の問いに
「決して、わたくしは、貧しくない」 と答えて、眸め
を、上げたときのその眸をもう一度、思い出して恥かしくなった。
(貧しいのは、自分たちの方であった。平家の公達きんだち
と生まれ、いったい、どれほどな福徳を身に持ったか。前太政入道さきのだじょうにゅうどうひとりを亡っては、一門、かくばかりうろたえているではないか。そのため、戦陣を駆けずりまわり、世に何を益しているか。からくも、栄華の余命を支えようと焦心しているだけのことではないか。・・・・それを思えば)
と、経正は、眼の前の一個の男に、なんともいえない気高けだか
さと、生の強さを、見るのであった。
世の波騒なみざい
も、権力も、毀誉きよ も褒貶ほうへん
も、栄華も、麻鳥には、なんのかかわりもない。どんなに血みどろを好む魔物でも、彼の無欲と愛情に徹した姿を、血の池へ追い込むことは出来ないであろう。
経正は、心のうちで、ほっと嘆声をもらした。この男に与える物、いつかの礼ぞといって、与えるような物を
── 自分は何も持ち合わせていないことを知った。
麻鳥は、心の王者。自分は心の貧者だった。 「ああ、何を施物せもつ
せんか」 と、迷ったのである。
「そうだ」
経正は、禰宜をかえりみて、ふと言った。
「宝器をけがす畏おそ
れはあるが、さきにお話の “仙童” をお貸し給わるまいか」
「おう、御興を催もよお
されましたか。おやすいことで」
と、老禰宜は起た
って、拝殿の内から、やがて一面の琵琶をささげて来た。 |